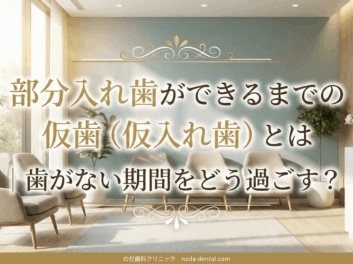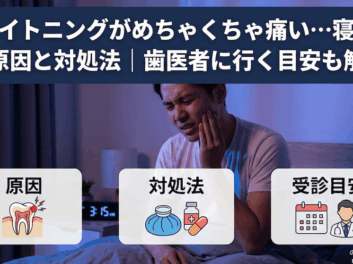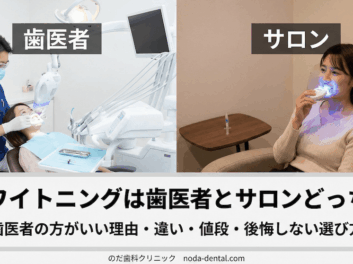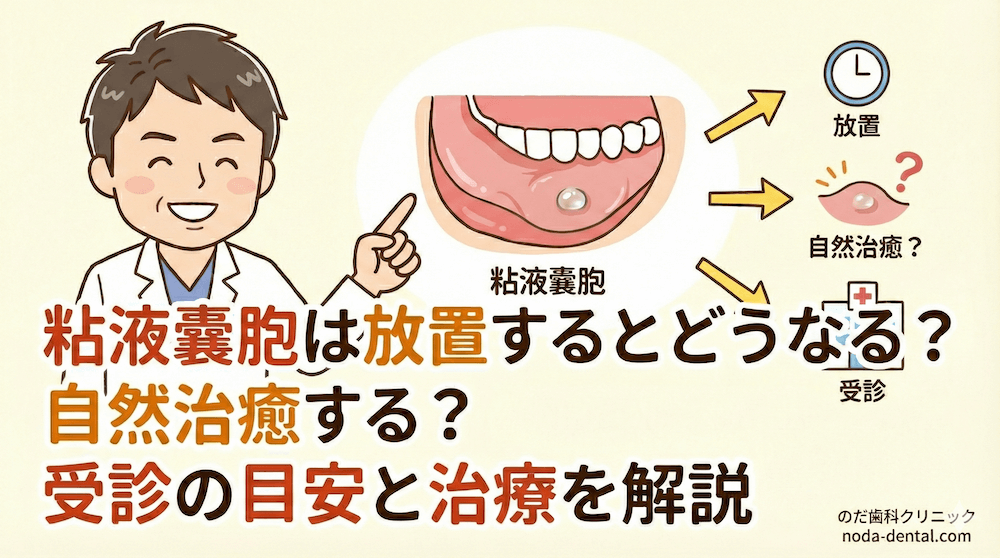歯医者の定期検診に行っている人の割合は?年代差・継続のコツまで徹底解説
2025.09.22

「歯医者の定期検診に行っている人は、実際どれくらいいるのだろう?」こうした疑問を抱かれる方は少なくありません。
最新の厚生労働省の歯科疾患実態調査(2025年)では、「過去1年以内に歯科検診を受けた人」は63.8%と報告されています。2022年の調査では58.0%であったことを考えると、着実に受診率が高まっているのがわかります。
背景には、予防歯科の浸透や健康意識の向上、歯周病と全身疾患の関連が広く知られるようになったことがあるといえるでしょう。ただし、年代や男女によって受診率には差があり、継続して通う工夫も欠かせません。
のだ歯科クリニックでは「できるだけ歯を残す」方針のもと、CTやマイクロスコープを用いた精密診断や担当衛生士制による長期的なサポート体制を整えています。本記事では、定期検診に通っている人の割合や背景、継続するメリット、そして当院の予防方針について詳しくご紹介します。
歯医者の定期検診に行っている人の割合

歯医者の定期検診を受けている人は、実際にどれくらいいるのでしょうか。最新の厚生労働省「歯科疾患実態調査(2025年)」によると、過去1年間に歯科検診を受けた人の割合は 63.8% でした。これは全国規模で行われている一次統計に基づく数字であり、もっとも信頼性の高いデータといえます。3年前の2022年調査では58.0%であったため、5ポイント以上の上昇が確認されました。わずか数年の間に受診率がこれだけ伸びていることは、日本における予防歯科の意識が着実に浸透している証拠と考えられます。
ここでいう「定期検診」とは、単に治療目的で来院するのではなく、症状がなくても予防や健康維持のために歯科医院で診察やクリーニングを受けることを指します。厚労省の定義では「過去1年以内に検診を受けた経験があるかどうか」が基準とされており、この明確な定義に基づいて集計されています。そのため「1年以上前に行った」「通院はしているが治療だけで検診は受けていない」といったケースはカウントされません。数値が持つ意味を正しく理解することが大切です。
また、今回の調査では男女差の傾向も明らかになっています。全体的に女性のほうが受診率が高く、年代別で見ても30代以降は特に女性の受診率が男性を上回る傾向が続いています。男性は仕事の多忙さや「症状がなければ行かなくてもよい」という意識が影響して受診率が低めにとどまる一方、女性は美容や健康管理への関心から定期的な通院を取り入れる人が多いと考えられます。
さらに年代別で見ると、若年層よりも中高年層で受診率が高い傾向が見られます。特に50代以降は歯周病や噛み合わせの問題など口腔トラブルが増えることもあり、検診を通じて早期に発見・対応しようとする意識が高まっているのです。一方で20〜30代では受診率が全体平均を下回り、「忙しい」「まだ自分には関係ない」といった理由で通院が後回しになってしまう現実があります。
こうしたデータからわかるのは、受診率が上昇しているとはいえ、年代や性別によってまだ差が存在するということです。今後は全世代で検診を「当たり前」とする意識の浸透が求められます。のだ歯科クリニックでは、精密診査に基づき「できるだけ歯を残す」方針を大切にしながら、患者さま一人ひとりに合わせた検診・予防プランを提供しています。検診の受診率が上がっている今こそ、通院を習慣にして将来のリスクを減らすことが重要なのです。
年代別・男女別の特徴|受診率が高いのは?
厚生労働省の2025年調査を詳しく見ると、定期検診の受診率には年代や男女による特徴がはっきりと表れています。まず年代別では、年齢が上がるほど受診率が高い傾向が明らかです。20〜30代では平均値を下回り、特に仕事や子育ての忙しさから「まだ自分には必要ない」と後回しにするケースが多いと考えられます。一方で40代以降になると歯周病や噛み合わせの不調といったトラブルが増え、受診率は徐々に上昇。50代以上では平均を上回り、健康維持の一環として検診を取り入れる人が増えています。
男女差に目を向けると、女性のほうが一貫して受診率が高い点が特徴的です。美容や健康への意識が高く、妊娠や更年期といったライフイベントを機に口腔ケアの必要性を感じる方が多いためと考えられます。対して男性は「症状がなければ行かなくてよい」という意識が根強く、受診率の伸びが鈍い傾向があります。このような違いを理解することは、自分自身の受診習慣を見直すきっかけにもつながるでしょう。
民間調査が示す「定期的」の自己認識
公的統計では「過去1年以内に検診を受けたかどうか」が明確な基準とされていますが、民間のアンケート調査では「定期的に通っている」と自己申告する人の割合はやや低めに出ています。例えば、ライオン株式会社が2022年に行った調査では「1年に1回以上は歯科検診を受けている」と答えた人は44%にとどまりました。これは厚労省の63.8%という数字と比べると大きな開きがありますが、その理由のひとつは「定期的」の定義の違いにあります。
自己申告ベースの調査では、「たまに行っているが直近1年は空いてしまった」という人が「定期的に通っていない」と認識して回答している可能性があります。また、そもそも検診と治療の区別が曖昧で、歯科医院に行っていても「治療だけだから検診ではない」と捉えるケースもあるようです。こうした調査結果からは、生活者自身が「予防のための通院」と「症状が出てからの治療」を混同している現状が見えてきます。一次統計とあわせて理解することで、受診行動の実態がより立体的に捉えられるでしょう。
日本の歯科検診受診率が上がっている背景

日本における歯科定期検診の受診率は、ここ15年ほどの間で確実に上昇してきました。2009年時点では40%台半ばにとどまっていた受診率が、2012年には50%前後、2016年には55%程度、そして2022年には58.0%にまで上昇。そして最新の2025年調査では63.8%と、ついに6割を大きく超える水準に達しています。このように緩やかではありながら一貫した上昇傾向が続いていることは注目すべき変化といえます。
背景にはいくつかの要因があります。第一に、予防歯科の重要性が社会全体に浸透してきたことが挙げられます。虫歯や歯周病が全身の健康と深く関わることが広く知られるようになり、「悪くなってから治す」のではなく「悪くなる前に防ぐ」という考え方が定着してきました。特に歯周病と糖尿病・循環器疾患との関連は、マスメディアや啓発活動を通じて広く伝えられています。
第二に、国の施策的な後押しも大きな役割を果たしました。学校や職場健診での口腔チェックの普及、8020運動の継続的な推進、そして高齢社会における「オーラルフレイル」予防の呼びかけなどが、人々に検診の必要性を意識させるきっかけとなっています。
さらに、歯科医院側の環境整備も受診率の向上に寄与しています。予約システムのオンライン化や土曜診療の導入などにより、忙しい人でも通いやすい体制が整えられました。また、定期検診を単なるチェックで終わらせず、歯面清掃やエアフローによるバイオフィルム除去、フッ素塗布といった具体的な予防処置と組み合わせることで、「行く価値」を実感しやすくなっています。
こうした複合的な要素が積み重なり、2009年から2025年にかけて受診率は約20ポイント近く上昇しました。今後も生活習慣病予防や健康寿命延伸の観点から、定期検診はますます欠かせない存在となるでしょう。
それでも検診の受診が途切れる理由は?
定期検診の受診率は年々上昇し、2025年の調査では63.8%に達しています。しかし一方で、全員が継続して通院できているわけではありません。実際には「途中で途切れてしまう」「わかっていても足が遠のく」といった現象が少なからず存在します。受診率の底上げが進むなかで、この“継続できない壁”をどう乗り越えるかが今後の課題といえるでしょう。
背景には、日本人特有の意識や生活習慣が関係しています。公的統計や民間調査を見ても、受診を続けられない理由は多岐にわたり、ライフスタイルや価値観によって現れ方が異なります。特に、時間や費用といった現実的な制約、そして「歯医者は痛いのでは」という心理的な抵抗感は、多くの人に共通する阻害要因です。さらに「治療が必要でなければ行かなくてもいい」という誤解が根強く、予防の意義が十分に理解されていないことも、定期検診の習慣化を妨げています。
このように、定期検診が社会的に推奨される状況にあっても、個々の患者さんにはまだ受診を続けにくい理由が残っているのです。次の章では、それぞれの要因をもう少し具体的に整理し、受診が中断されやすい背景を詳しく見ていきましょう。
時間・費用・「痛そう」など心理的ハードル
定期検診が大切と分かっていても、実際に通うとなると「なかなか続かない」という声が少なくありません。その代表的な理由の一つが時間の制約です。仕事や家事に追われるなかで「平日の昼間に行けない」「予定が合わない」と先送りになってしまうケースは多く見られます。また費用についても「痛みがないのにお金を払うのはもったいない」と感じ、優先度を下げてしまう人が一定数存在します。
加えて、「歯医者は痛そう」「怖い」というイメージも根強いものです。実際には定期検診で行うのは歯面清掃や歯周ポケットのチェックが中心で、痛みを伴う処置はほとんどありません。しかし過去の治療経験や漠然とした不安から、足が遠のいてしまう方がいるのも現実です。
こうした時間・費用・心理的ハードルは、多くの患者さんに共通する受診阻害要因です。次では、これら以外にも受診を中断させてしまう考え方について触れていきます。
治療がないと「行かなくてよい」と考えがち
定期検診が途切れるもう一つの大きな理由は、「痛みや症状がなければ行かなくてもよい」と考えてしまう点です。虫歯や歯周病は初期段階では自覚症状が乏しく、進行していても気づかないことが少なくありません。そのため「自分は大丈夫」と思い込み、受診を先延ばしにしてしまう方が多いのです。
しかし、実際には症状が出たときには病状がかなり進んでいることが多く、治療の負担や抜歯のリスクが高まってしまいます。逆に、症状が出る前に検診で異変を発見できれば、最小限の処置で済み、歯を長く残すことが可能です。
「治療がなければ不要」という考え方は、口腔の健康を守るうえで大きな落とし穴です。検診を予防のための行動として捉え直すことが、継続の第一歩となります。
定期検診を続けるメリット

定期検診を続けることには、医療的にも経済的にも多くの恩恵があります。まず医療面では、虫歯や歯周病を早期に発見し、軽度のうちに処置できることが大きな利点です。症状が進んでから治療を受けると、歯を大きく削ったり、場合によっては抜歯に至ることもありますが、定期検診を受けていればそのリスクを抑えることが可能になります。さらに、歯周病と全身疾患の関連が広く知られるようになり、口腔を守ることが全身の健康維持につながる点も注目されています。
経済的にも、定期検診の継続は将来的な治療費の軽減につながります。初期段階での処置は費用も通院回数も少なく済みますが、重症化するとインプラントや入れ歯といった大がかりな治療が必要となり、経済的な負担が急増します。「予防に通う」こと自体が、長期的には大きな節約となるのです。
また、自分の歯を保つことは生活の質の維持にも直結します。噛む力や発音の明瞭さ、さらには見た目の若々しさなど、日常の快適さを支える基盤となります。
このように、定期検診には医療・経済・生活の三つの側面からメリットがあります。次では、その中でも特に重要な「早期発見による重症化・抜歯回避」の効果について詳しく見ていきましょう。
虫歯・歯周病の早期発見→重症化・抜歯の回避
定期検診を受ける最大のメリットは、虫歯や歯周病を早期に発見できることです。これらの病気は初期段階では痛みなどの自覚症状がほとんどなく、気づいたときには進行しているケースが少なくありません。定期的に歯科医師や歯科衛生士によるチェックを受ければ、わずかな変化でも見逃さず、軽度の処置で改善できる可能性が高まります。
たとえば虫歯であれば、小さなうちに治療すれば削る範囲を最小限に抑えられますし、歯周病であれば歯ぐきの腫れや出血の段階で発見できれば、歯を失うリスクを大幅に下げられます。逆に、症状が出てからの受診では抜歯や大がかりな治療が必要になることもあり、時間的・経済的な負担も大きくなってしまいます。
つまり、定期検診は「悪化を防ぐ」だけでなく「歯を残す」ための最も効果的な方法です。のだ歯科クリニックでも、CTやマイクロスコープを用いた精密診断で小さな異変を早期に把握し、できるだけ抜歯を避ける治療方針を重視しています。
長期コストの抑制とQOL(見た目・咀嚼・発音)
定期検診を続けることは、医療費の面でも生活の質の面でも大きな効果があります。虫歯や歯周病が重症化してから治療を受ける場合、抜歯やインプラント、入れ歯などの大規模な処置が必要になることがあり、費用も通院回数も一気に増加します。しかし、定期検診で早期に異常を見つけられれば治療は最小限で済み、長期的にみると大きなコスト削減につながります。
また、自分の歯を守ることは見た目や機能の維持にも直結します。歯が残っていれば自然な笑顔や表情が保たれるだけでなく、しっかりと噛めることで食事を楽しみ、栄養バランスも整えやすくなります。発音も明瞭になり、会話の快適さや社会生活での自信にもつながるのです。
つまり定期検診は、将来の経済的負担を軽くするだけでなく、日々の暮らしをより豊かにするための基盤ともいえるでしょう。
定期検診に通わない場合の考えうるリスク
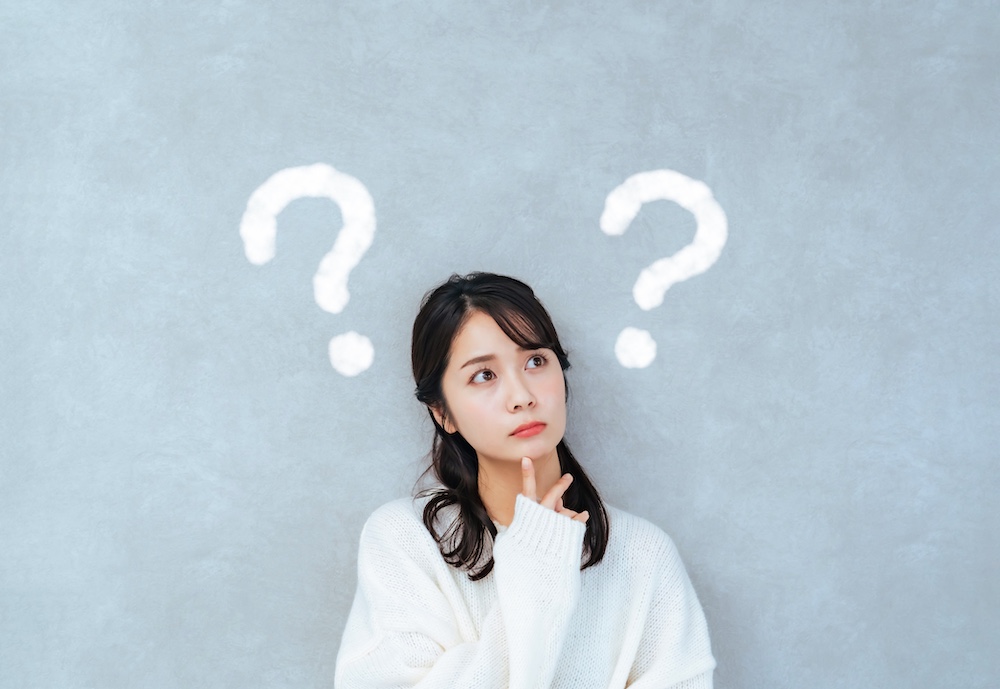
定期検診に通わない状態が続くと、口腔内にはさまざまなリスクが積み重なっていきます。虫歯や歯周病は進行するまで自覚症状が乏しいため、「痛みがないから大丈夫」と思っているうちに悪化しているケースが多いのです。検診を受けないまま放置すると、気づいたときにはすでに歯を失う一歩手前まで進んでいた、ということも珍しくありません。
さらに、口腔の健康は全身にも影響します。歯周病菌が血流に乗って全身に広がると、糖尿病や心疾患、脳血管疾患などとの関連が報告されています。つまり、定期検診を怠ることは「歯の問題」にとどまらず、生活の質や健康寿命にも直結する重大なリスクなのです。
このように、検診を受けないことで将来的にどのような不利益が生じるかを理解しておくことはとても大切です。次では、具体的に「歯周病や虫歯の進行による口腔リスク」と「全身健康との関連」に分けて詳しく確認していきましょう。
歯周病・う蝕の進行/将来の抜歯・欠損リスク
定期検診を受けずに過ごすと、虫歯(う蝕)や歯周病は知らないうちに進行してしまいます。虫歯は初期であれば小さな充填処置で治せますが、放置すると神経にまで達し、激しい痛みや根管治療、さらには抜歯が必要になることもあります。歯周病も同様に、初期の歯ぐきの炎症を見逃すと骨の吸収が進み、最終的には歯が支えを失って自然に抜けてしまうケースも少なくありません。
一度失った歯は元には戻らず、入れ歯やブリッジ、インプラントといった補綴治療が必要となります。これらは機能を補う手段として有効ですが、自分の歯に勝るものではありません。さらに治療費や通院負担が大きくなることを考えると、失う前に守ることがいかに重要かがわかります。
つまり、検診を怠ることは「歯を失うリスクを高める行動」にほかなりません。定期的なチェックを受けることが、将来の欠損を防ぎ、自分の歯で長く生活するための鍵となるのです。
全身健康との関連(糖尿病・循環器など)
歯科検診を受けずに口腔内のトラブルを放置すると、影響は口の中だけにとどまりません。近年の研究では、歯周病と糖尿病や心筋梗塞、脳梗塞といった循環器疾患との関連が数多く報告されています。歯周病の炎症によって細菌や炎症物質が血流に入り込むと、全身の血管や代謝に悪影響を及ぼすと考えられているのです。
実際に、糖尿病患者は歯周病が重症化しやすく、逆に歯周病を治療すると血糖コントロールが改善するという報告もあります。また、歯を失った人は噛む力が低下し、食生活の偏りから栄養状態や体力の低下を招きやすい点も見逃せません。
このように、口腔の健康は全身の健康と密接に結びついています。定期検診を怠ることは、将来的な生活習慣病リスクを高める要因となるため、予防の観点からも継続的な受診が欠かせません。
定期検診にはどれくらいの頻度で行けばよい?

定期検診の重要性は理解していても、「実際にはどのくらいの間隔で通えばよいのか」と迷う方は少なくありません。一般的には3〜6か月ごと、少なくとも年に1回の受診が推奨されていますが、最適な頻度は年齢や口腔内の状態、過去の治療歴によって変わります。たとえば、歯周病のリスクが高い人や治療中の方は短い間隔が望ましい一方、良好な口腔環境を維持できている人は半年から1年に一度の検診でも十分なケースがあります。
厚労省の調査や各種ガイドラインでも、定期検診は「一律の間隔」ではなく「個々のリスクに応じた調整」が基本とされています。虫歯や歯周病の進行スピードは人によって異なり、同じ年齢でも生活習慣やセルフケアの状況によって必要な通院頻度は変わるのです。
また、矯正治療中やインプラント治療を受けた方などは、治療の安定性を保つために1〜3か月ごとの短い間隔でのメンテナンスが必要になる場合もあります。こうした「個別性」を理解することが、定期検診を効果的に続けるうえで欠かせません。
このように、定期検診の頻度は一律に決められるものではなく、口腔内のリスクやライフステージに合わせて調整していく必要があります。次では、一般的な目安と、特に短い間隔で通うべきケースについて詳しく見ていきましょう。
一般的な目安:3〜6か月・年1回の基準と例外
定期検診の基本的な目安は「3〜6か月に1回」、少なくとも「年に1回」とされています。これは歯垢や歯石が数か月で再び蓄積することや、歯周病の進行が半年単位で進むケースがあるためです。定期的に専門的なチェックを受けることで、口腔環境を安定的に保つことが可能になります。
ただし、この目安はあくまでも一般的な基準であり、例外もあります。例えば歯周病が軽度でセルフケアもしっかりできている方は、半年に一度でも十分効果的です。一方、歯肉炎の兆候が見られる方やプラークコントロールが不十分な方は、3か月ごとの受診が推奨されます。また、歯並びやかみ合わせの問題がある場合も清掃不良が起こりやすく、短い間隔での管理が望まれます。
つまり、定期検診の間隔は「誰にでも同じ」ではなく、口腔状態やセルフケアの習慣によって柔軟に調整されるべきなのです。次では、再発リスクが高い人や矯正・インプラント治療中の方など、特に短い間隔で通う必要があるケースを見ていきましょう。
再発リスクが高い人・矯正中・インプラント治療歴がある人
一般的な受診間隔は3〜6か月が目安とされていますが、特に短いスパンでの定期検診が望ましい人もいます。代表的なのは、虫歯や歯周病を繰り返しやすい「再発リスクが高い人」です。治療歴が多い方や歯ぐきの状態が安定していない方は、1〜3か月ごとのチェックで早期に異常を見つけることが重要になります。
また、矯正治療中の方も注意が必要です。矯正装置の周囲は汚れがたまりやすく、セルフケアだけでは十分に清掃できないことがあります。定期的に専門的なクリーニングを受けることで、虫歯や歯肉炎のリスクを防ぐことができます。
さらに、インプラント治療歴のある方も短い間隔での管理が欠かせません。人工歯根は天然歯と異なり、インプラント周囲炎が進行しても気づきにくい特徴があります。定期的な検診によって清掃状態や骨の安定性を確認することで、長期的にインプラントを維持することが可能になります。
のだ歯科クリニックの定期検診(予防メンテナンス)

のだ歯科クリニックでは、定期検診を「病気を早期に見つけるため」だけでなく、「できるだけ歯を残すための積極的な予防の場」と位置づけています。歯は一度失うと元には戻らず、入れ歯やインプラントで補うことはできますが、天然歯に勝るものはありません。そのため当院では、精密診査を通じてわずかな異変も見逃さず、可能な限り抜歯を避ける診療方針を大切にしています。
また、精密機器の活用も大きな特長です。歯科用CTや拡大鏡、マイクロスコープを用いて、目視では確認できない細部までチェックします。これにより診断の確実性が高まり、早期の対応や治療の選択肢が広がります。さらに、担当衛生士制を導入しているため、患者さま一人ひとりの経過を長期的に追いながら、その方に合ったセルフケア方法や生活習慣改善の提案が可能です。
予約システムの整備や土曜診療、Web予約の導入により、忙しい方でも通いやすい体制を整えている点も当院ならではの強みです。単に検診を受けるだけでなく、生活の一部として無理なく続けていただけるよう工夫しています。
このように、のだ歯科クリニックの定期検診は「保存志向」「精密診断」「長期的サポート」「通いやすさ」の四つを柱に据えています。次では、それぞれの具体的な取り組みについて掘り下げてご紹介します。
できるだけ歯を抜かない診療×精密診断(CT・拡大視野)
のだ歯科クリニックでは「できるだけ歯を残す」ことを治療方針の中心に据えています。むやみに抜歯を行うのではなく、CTやマイクロスコープ、拡大鏡といった精密機器を駆使し、歯の保存が可能かどうかを丁寧に見極めます。これにより、肉眼では判断が難しい細部の状態を確認でき、わずかな亀裂や初期の炎症も見逃しません。
精密診断を行うことで、虫歯や歯周病を早期に発見し、最小限の処置で改善できる可能性が高まります。神経を残す治療や、歯周組織を温存する処置が選択できるのもこの取り組みの大きな利点です。患者さまにとっては、歯を失うリスクを減らすだけでなく、治療の負担や費用も軽減できることにつながります。
「抜歯は最後の手段」という考えのもと、当院は精密診査を徹底し、長期的に自分の歯で過ごせるようサポートしています。
担当衛生士制・生活習慣に合わせたセルフケア設計
のだ歯科クリニックでは、患者さま一人ひとりに担当衛生士を配置しています。毎回同じ衛生士が経過を追うことで、小さな変化にも気づきやすく、長期的な予防計画を立てやすいのが特徴です。単に歯石を取るだけでなく、生活習慣やセルフケアの癖を把握したうえで、その方に合った改善策を一緒に考えます。
たとえば、忙しい方には短時間で効率的に行えるブラッシング方法を提案したり、歯周病リスクが高い方にはフロスや洗口液の効果的な活用を勧めるなど、生活背景に合わせた指導を行います。また、定期的な記録をもとに「前回より出血が減っている」「磨き残しが少なくなった」といった変化を共有することで、患者さまのモチベーション維持にもつながります。
担当衛生士制は、患者さまと医院が二人三脚で予防に取り組むための大切な仕組みです。継続的な関係性を築くことで、検診を習慣として続けやすくなります。
予約設計・土曜診療・Web予約など通いやすい仕組みづくり
のだ歯科クリニックでは、患者さまが定期検診を無理なく続けられるよう、通院の利便性にも配慮しています。
平日だけでなく土曜も診療を行っているため、平日の通院が難しい方でも受診しやすい体制です。さらに、Web予約に対応しているため、スマートフォンやパソコンから24時間いつでも簡単に予約できます。
こうした仕組みがあることで、忙しい方でも検診を継続しやすくなっています。
定期検診を続けるためのコツ
定期検診の重要性を理解していても、実際には「つい行きそびれてしまう」という方は少なくありません。検診を生活習慣として根付かせるためには、無理なく続けられる仕組みや工夫が欠かせます。近年の調査でも、受診が途切れる理由には「時間の調整が難しい」「忘れてしまう」「必要性を実感できない」といった声が挙げられており、それらを解消する実務的な工夫が継続率向上につながります。
具体的には、次回の予約を先に押さえてしまうことや、スマートフォンのカレンダーに予定を入れておくことが有効です。また、家族で同じ日に受診するようにすれば通院の手間を減らすことができます。さらに、費用や時間の見通しを持てるようにしておくと、「負担が大きいのでは」という不安を軽減でき、受診をためらいにくくなるでしょう。
このように、定期検診を習慣化するには「仕組み化」と「見通しの明確化」が鍵となります。次では、継続率を高めるための具体的な工夫を二つの視点から詳しくご紹介します。
次回予約の先取り/カレンダー連携/家族同日受診
定期検診を途切れさせないためには、受診の予定を「仕組み化」してしまうことが効果的です。検診後にその場で次回の予約を先取りしておけば、忙しい日常の中でも予定が後回しになるのを防げます。加えて、スマートフォンのカレンダーやリマインダー機能と連携させることで、「うっかり忘れてしまう」リスクを減らすことができます。
また、家族で同じ日に受診するのも効率的な方法です。家族全員が一緒に検診を受ければ、通院の手間をまとめられるだけでなく、お互いに口腔ケアへの意識を高め合うきっかけにもなります。こうした日常的な工夫を取り入れることで、定期検診はより続けやすい習慣へと変わっていきます。
費用・時間の見通しを持つ
定期検診を習慣化するには、費用や時間の不安を解消しておくことも大切です。「どのくらい費用がかかるのか」「どれくらいの時間で終わるのか」が分かっていれば、受診に対する心理的なハードルはぐっと下がります。例えば、短時間で行えるPMTC(専門的クリーニング)であれば、忙しい方でも通いやすく、口腔内を清潔に保つ効果を実感できます。
さらに、平日夕方や土曜日など、多様な時間帯に診療枠がある医院を選ぶことで、予定に組み込みやすくなります。こうした「負担の見通し」を持てる環境を整えることが、定期検診を無理なく続けるための重要なポイントとなるのです。
大阪府高石市エリアでお探しの方へ
のだ歯科クリニックは、大阪府高石市を中心に地域の皆さまの口腔健康を支えている総合歯科医院です。定期検診だけでなく、虫歯・歯周病・根管治療・入れ歯・インプラント・矯正治療など幅広い診療に対応しており、ご家族そろって安心して通っていただけます。
症状が気になる方には、関連ページをあわせてご覧いただくと理解が深まります。たとえば「歯ぐきからの出血」「しみる」「口臭が気になる」といった症状別ページでは、それぞれの原因や治療法を解説しています。また、治療内容ごとに「一般歯科」「歯周病治療」「根管治療」「メンテナンス」などのページもご用意しており、詳しい情報にアクセスしやすくなっています。
定期検診の受診率は全国的に高まりつつありますが、実際にどの医院を選ぶかは大切なポイントです。高石市エリアで信頼できる歯科医院をお探しの方は、ぜひ当院の各ページをご覧いただき、受診の参考になさってください。
まとめ:定期検診の「受診率が上がる今」、将来の抜歯リスクを減らすチャンス

最新の厚労省調査によれば、歯科定期検診の受診率は63.8%と過去最高水準に達し、日本全体で予防意識が高まっています。とはいえ年代や性別による差、そして「治療がなければ行かなくてよい」と考える誤解は依然として残っており、誰もが継続できているわけではありません。
定期検診を続けることで、虫歯や歯周病を早期に発見し、重症化や抜歯を避けられる可能性が高まります。さらに、治療費の抑制や見た目・咀嚼機能の維持といった生活の質にも直結するため、長期的に大きな価値を持ちます。
のだ歯科クリニックでは、「できるだけ歯を残す」という保存志向の診療を基盤に、CTやマイクロスコープを活用した精密診断、担当衛生士制による長期的サポートを行っています。受診率が伸びている今こそ、将来の抜歯リスクを減らすチャンスです。気になる症状がある方、前回の検診から間が空いてしまった方は、ぜひ当院にご相談ください。
関連記事
2026.01.14
部分入れ歯ができるまでの仮歯(仮入れ歯)とは|歯がない期間をどう過ごす?
2025.12.31
ホワイトニングがめちゃくちゃ痛い…寝れない原因と対処法|歯医者に行く目安も解説
2025.12.26
ホワイトニングは歯医者とサロンどっち?歯医者の方がいい理由・違い・値段・後悔しない選び方
2025.12.19