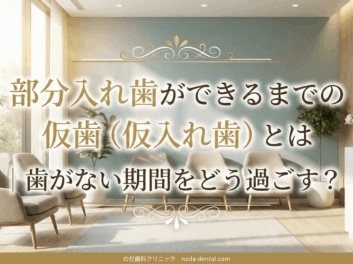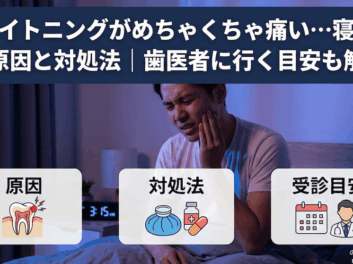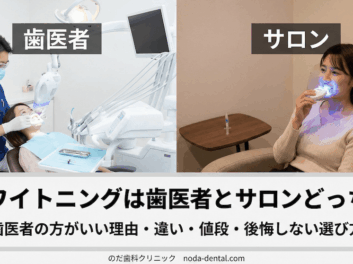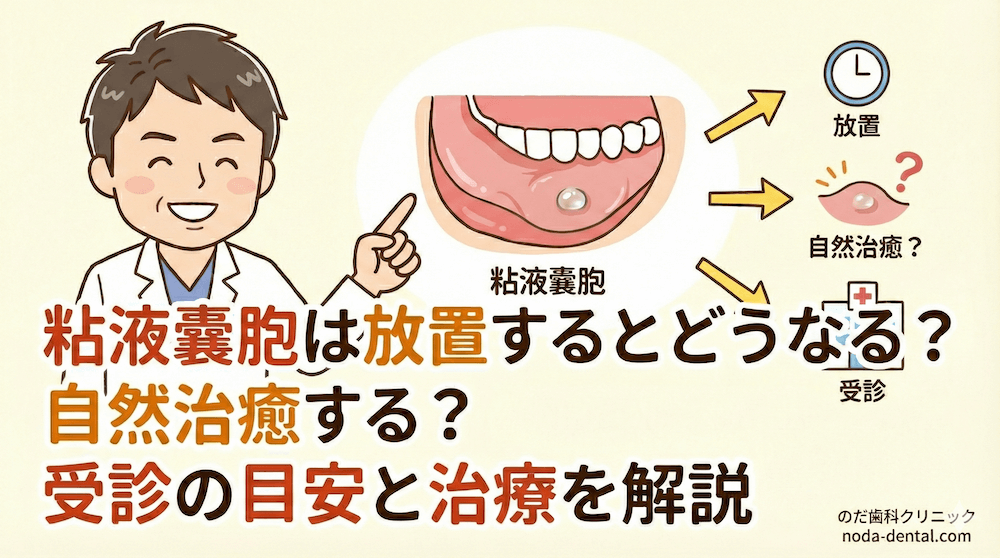虫歯と歯周病の違いを徹底解説|原因・症状・治療法と予防法
2025.09.15

「虫歯と歯周病、どちらが怖いの?どう違うのだろう」と不安に感じている方は少なくありません。どちらも歯を失う大きな原因であり、早期発見と適切な治療が欠かせない疾患です。しかし、原因や進行の仕方、治療法や予防法には明確な違いがあるのです。違いを正しく理解することで、適切に対処でき、将来的に歯を守ることにつながります。
本記事では「虫歯と歯周病の違い」をわかりやすく整理し、原因・症状・治療法・予防法の流れで解説していきます。さらに、のだ歯科クリニックの治療方針にも触れながら、「できるだけ歯を抜かずに守る」「精密診断による確かな見極め」といった当院の取り組みをご紹介します。
放置してしまうと取り返しのつかない結果を招くこともあります。ぜひ最後までご覧いただき、ご自身のお口の健康管理にお役立てください。
虫歯と歯周病の基本的な違い

「虫歯と歯周病はどう違うのだろう」と迷う方は多いのではないでしょうか。どちらも歯科医院でよく耳にする代表的な病気ですが、原因や現れる症状、そして進行の仕方には大きな違いがあるのです。虫歯は歯そのものが溶けていく病気であり、歯周病は歯を支える歯ぐきや骨が壊されていく病気といえます。つまり、ターゲットとなる場所が異なる点が最も大きな違いなのです。
虫歯は口腔内に存在する細菌(ミュータンス菌など)が糖を代謝し、酸を作り出すことで歯を溶かしていきます。一方、歯周病は歯と歯ぐきの境目に付着する歯周病菌が原因で、炎症を起こしながら歯周組織を徐々に破壊していきます。このように、同じ「プラーク(歯垢)」が関わっていても、細菌の種類や影響を受ける部位が違うのです。
また、症状の現れ方も対照的です。虫歯では「歯の痛み」や「冷たいものがしみる」といった自覚症状が早い段階から現れることが多いのに対し、歯周病は初期には痛みを感じにくく、歯ぐきの腫れや出血といったサインに気づかないまま進行するケースが少なくありません。そのため、歯周病は「沈黙の病気」とも呼ばれているのです。
このように、虫歯と歯周病は原因・症状ともに異なる病気であり、放置すればどちらも歯を失う深刻な結果につながります。次では、まず「原因の違い」と「症状の違い」について詳しく見ていきましょう。
原因の違い
虫歯と歯周病は、いずれもプラーク(歯垢)に潜む細菌が大きな要因となりますが、関わる菌の種類や働きが異なります。虫歯は主にミュータンス菌などの虫歯菌が糖分を分解して酸を生み出し、その酸が歯の表面のエナメル質を溶かすことで進行します。一方、歯周病は歯周病菌が歯と歯ぐきの境目にたまり、炎症を起こすことで歯肉や骨を破壊していきます。
また、虫歯は甘い飲食物の摂取頻度や歯磨き不足が強く影響するのに対し、歯周病は喫煙やストレス、全身疾患など生活習慣や体質とも深く関係しています。つまり、同じプラーク由来でも原因菌とリスク因子は大きく異なるのです。
症状の違い
虫歯と歯周病では、自覚できる症状の出方が大きく異なります。虫歯の場合、初期には歯の表面が白く濁ったり黒ずんだりしますが、進行すると「冷たいものがしみる」「噛むと痛い」といった感覚が現れ、さらに進むと強い痛みや神経への炎症を引き起こします。比較的早期から不快症状が出やすい点が特徴です。
一方、歯周病は初期段階では痛みをほとんど感じないまま進行しやすく、歯ぐきの腫れや出血、口臭などで気づくことが多いです。さらに悪化すると歯がぐらつき、最終的には歯を失うことにつながります。この「痛みが少なく進行する」点が虫歯との大きな違いなのです。
虫歯の特徴と進行

虫歯は、歯の表面から内部へと少しずつ進行していく病気です。口腔内に常在する虫歯菌が食べ物の糖を栄養源として酸を生み出し、その酸によって歯のエナメル質が溶かされることから始まります。初期には白く濁ったような変化しか見られず痛みもありませんが、進行すると黒ずみや穴が目立つようになり、冷たいものや甘いものがしみるといった不快な症状を引き起こします。
さらに進むと、虫歯は象牙質を経て歯の神経にまで到達し、強い痛みを伴うようになります。ここまで悪化すると治療は複雑になり、根管治療などで神経を取り除く必要が出てきます。場合によっては歯を保存できず、抜歯に至るケースもあります。つまり、虫歯は「進行性」であり、放置すれば必ず悪化する病気なのです。
虫歯の怖さは、そのスピードと生活の質への影響にもあります。痛みによって食事が楽しめなくなったり、見た目の印象を損ねたりすることも少なくありません。特に奥歯は噛む力を支える大切な役割を担っているため、失うと他の歯にも大きな負担がかかります。
当院では、こうしたリスクを最小限に抑えるため「なるべく削らず、できるだけ歯を残す」治療方針を重視しています。歯科用CTや拡大鏡を活用した精密診断により、保存可能な歯を見極め、患者様にとって最適な治療法を選択しています。虫歯を早期に発見し、正しい段階で介入することが、歯の寿命を延ばすために欠かせないのです。
次では、虫歯の進行をさらに詳しく「初期の症状と進行段階」「放置した場合のリスク」「治療方法」に分けて解説していきます。
初期の症状と進行段階
虫歯は、初期の段階では自覚症状が乏しいため見逃されやすい病気です。最初は歯の表面に白く濁った「ホワイトスポット」が現れ、これはエナメル質が脱灰しているサインです。この段階では痛みもなく、見た目の変化もわずかなので気づきにくいのです。
やがて進行すると歯の表面が黒ずんだり、小さな穴が生じたりします。この頃から「冷たいものがしみる」といった症状が出始めます。さらに象牙質に達すると刺激が神経に伝わりやすくなり、温かいものや甘いものでも強い痛みを感じるようになります。放置すると虫歯は歯髄に到達し、ズキズキとした痛みが続き、神経を守ることが難しくなってしまいます。
放置した場合のリスク
虫歯を放置してしまうと、軽度の不快感だけでなく、歯そのものを失う深刻な結果につながります。初期段階では小さな穴やしみる程度でも、やがて虫歯は歯の内部に進み、神経(歯髄)まで炎症が広がります。神経が感染すると激しい痛みを伴い、根管治療が必要となります。治療を行わなければ、炎症は歯の根の先や周囲の骨に広がり、膿がたまって顔が腫れるなど全身に悪影響を及ぼすこともあるのです。
さらに進行すれば、歯を残すことができず抜歯が避けられなくなります。歯を1本でも失うと噛み合わせのバランスが崩れ、隣の歯や反対側の歯にも負担がかかり、連鎖的に口腔機能を損なうリスクがあります。また、見た目の変化や発音への影響、食事の制限によって生活の質が低下することも少なくありません。
このように、虫歯は「時間が解決する病気」ではなく、放置すればするほど治療が難しくなるのです。早期に発見し、適切な治療を受けることが歯の寿命を延ばす最大のポイントといえます。
治療方法
虫歯の治療は、その進行度によって大きく変わります。初期の段階であれば、歯を削らずに再石灰化を促す「予防的治療」で済む場合があります。フッ素塗布やフッ素洗口、生活習慣の改善により、エナメル質の脱灰を修復できることもあるのです。この段階での介入は痛みも少なく、歯の寿命を大きく延ばすことにつながります。
虫歯が進行して小さな穴が生じた場合は、虫歯部分を最小限に取り除き、レジン(樹脂)などで充填します。中等度に進んだケースでは、削る範囲が広がり、インレーやクラウンといった修復物を用いて歯の形を補うことが必要です。さらに深く進んで神経に達してしまった場合は、根管治療を行い、感染した神経を取り除いたうえで内部を清掃・消毒し、最終的にクラウンで補強する流れになります。
重度の虫歯では、歯の保存が難しく抜歯となることもありますが、のだ歯科クリニックでは「できるだけ歯を残す」ことを基本方針としています。歯科用CTや拡大鏡・マイクロスコープを駆使して精密に診断し、残せる可能性がある歯を見極め、根管治療や補綴の工夫で保存を試みます。こうした取り組みにより、患者様が長く自分の歯で噛めるようサポートすることを大切にしているのです。
歯周病の特徴と進行

歯周病は「歯を支える組織」に起こる病気であり、日本人が歯を失う最大の原因といわれています。虫歯が歯そのものを壊す病気であるのに対し、歯周病は歯ぐきや歯槽骨といった歯の土台を徐々に破壊していく点が大きな特徴です。初期にはほとんど自覚症状がないため、気づかないうちに進行してしまうことが多く、「沈黙の病気」と呼ばれることもあります。
歯周病の始まりは、歯と歯ぐきの境目にプラークがたまり、歯周病菌が繁殖することから始まります。細菌によって歯肉が炎症を起こすと、赤く腫れたり、歯磨きで出血したりする「歯肉炎」の状態になります。この段階であれば適切なケアや歯科でのクリーニングにより回復が可能ですが、放置すると炎症はさらに奥へと進み、歯を支える骨(歯槽骨)が溶け出す「歯周炎」に移行します。
歯周炎が進行すると、歯ぐきが下がって歯が長く見えたり、歯と歯の間にすき間ができたりするなど、見た目にも変化が現れます。やがて歯がぐらつき、噛む力に耐えられなくなって最終的には自然に抜けてしまうこともあるのです。このように、痛みが目立ちにくいにもかかわらず、進行すれば歯を失う深刻な結果につながるのが歯周病の恐ろしさといえます。
さらに、歯周病は口腔内だけの問題にとどまらず、全身の健康とも関係していることが近年の研究で明らかになっています。糖尿病や心疾患、早産などとの関連が報告されており、生活習慣病と密接に関わる「全身疾患のリスク因子」ともいえるのです。そのため、歯周病対策は口腔の健康を守るだけでなく、全身の健康維持にも欠かせません。
のだ歯科クリニックでは、歯周病を早期に発見・治療するために歯科用CTや拡大鏡を用いた精密診断を行い、担当衛生士による長期的なサポート体制を整えています。また、エアフローを活用した歯面清掃や、フッ素洗口・ポイックウォーターなどの先進的な予防法も導入し、再発を防ぐ取り組みを徹底しています。
次では、歯周病をさらに詳しく「初期症状と段階」「放置した場合のリスク」「治療方法」に分けて解説していきます。
初期症状と段階
歯周病はごく初期の段階では痛みを伴わないため、気づかれにくい病気です。最初に見られるのは歯ぐきの赤みや軽い腫れで、歯磨きの際に少量の出血があることもあります。これが「歯肉炎」と呼ばれる状態で、炎症が歯ぐきの表面にとどまっている段階です。この時点であれば、正しい歯磨きや歯科医院でのクリーニングにより健康な状態に戻すことが可能です。
しかし、放置すると炎症は歯ぐきの奥にまで広がり、「歯周炎」へと進行します。歯周ポケットと呼ばれる歯と歯ぐきのすき間が深くなり、細菌が繁殖しやすい環境ができてしまいます。やがて歯を支える骨(歯槽骨)が溶け始め、歯ぐきが下がって歯が長く見えるようになったり、歯の間に食べ物が詰まりやすくなったりするのです。
このように歯周病は段階的に進行し、気づいたときにはすでに歯を支える組織が失われていることも少なくありません。早期に変化を察知し、適切に対処することが歯を守るための第一歩となります。
放置した場合のリスク
歯周病を放置すると、時間の経過とともに歯を支える組織が破壊され、取り返しのつかない結果を招きます。初期の歯肉炎の段階であれば比較的容易に改善できますが、進行して歯周炎になると歯槽骨が徐々に溶けていき、歯がぐらつき始めます。進行に比例して噛む力が低下し、やがて日常生活にも支障が出るようになります。
さらに悪化すると、歯は自力で支えられなくなり、最終的には自然に抜け落ちてしまうこともあります。歯を失うと見た目や発音への影響だけでなく、食事の制限による栄養不足や消化不良など全身の健康にも影響を及ぼします。また、歯周病は糖尿病や心筋梗塞、脳梗塞などの生活習慣病と関連があることも報告されており、口腔内にとどまらないリスクを抱えているのです。
このように、歯周病を放置することは単に「歯を失う」だけではなく、生活の質や全身の健康に深刻な影響を及ぼします。早期発見と適切な治療を受けることが何よりも重要なのです。
治療方法
歯周病の治療は、進行度に応じて段階的に行われます。軽度の歯肉炎であれば、毎日の歯磨き改善や歯科医院でのプロフェッショナルクリーニングによって健康な状態に回復できることが多いです。特に歯石は自宅でのケアでは取り除けないため、定期的なスケーリング(歯石除去)が欠かせません。
中等度に進行した歯周炎では、歯周ポケットの奥に潜む細菌や歯石を徹底的に取り除く「スケーリング・ルートプレーニング」を行います。これは歯根の表面を滑らかにして再び汚れが付きにくい状態に整える処置であり、炎症の改善に大きな効果を発揮します。この段階でしっかりと治療を行えば、歯の動揺を抑え、歯を残せる可能性が高まります。
重度の場合には、歯周ポケットが深く、通常の処置では改善が難しいため「歯周外科手術」が検討されます。歯ぐきを切開して奥深くに付着した歯石や感染組織を直接除去し、組織の再生を促す方法です。また、歯周組織再生療法など先進的な治療を組み合わせることで、失われた骨や歯ぐきの回復を目指すことも可能です。
のだ歯科クリニックでは、精密診断をもとに最小限の負担で効果的な治療を行うことを重視しています。担当衛生士が患者様一人ひとりを長期的にサポートし、治療後も再発を防ぐために定期的なメンテナンスや予防プログラムを継続。さらに、エアフローによる歯面清掃やポイックウォーター・フッ素洗口の活用など、先進的なアプローチも取り入れています。こうした多角的な取り組みによって、患者様が安心して歯を残せるよう努めているのです。
虫歯と歯周病の「痛み」の違い

虫歯と歯周病は、いずれも放置すれば歯を失う病気ですが、痛みの現れ方は大きく異なります。
虫歯は比較的早期から自覚症状が出やすく、冷たいものや甘いものがしみることから始まり、進行とともに神経へ炎症が広がって強い痛みを伴います。
これに対して歯周病は「沈黙の病気」と呼ばれるように初期は痛みがほとんどなく、歯ぐきの腫れや出血といった軽いサインから進行します。
気づかぬうちに歯を支える骨が破壊され、噛むと違和感や痛みを覚える段階になってから発見されることも少なくありません。次では、その痛みがどのように生じるのか、その仕組みを解説します。
痛みの発生メカニズム
虫歯と歯周病では、痛みが生じる仕組みが大きく異なります。虫歯の場合、口腔内の細菌が糖を分解して酸を生み出し、エナメル質や象牙質を溶かしていきます。初期には自覚症状がありませんが、進行すると象牙質に刺激が伝わりやすくなり、冷たいものや甘いものがしみるようになります。さらに神経(歯髄)に炎症が及ぶと、ズキズキとした強い痛みが続くのが特徴です。
一方、歯周病は歯周病菌が歯ぐきに炎症を起こし、歯肉や歯槽骨といった歯を支える組織を破壊していきます。初期には痛みを感じにくいのですが、進行すると歯ぐきの腫れによる圧迫感や、噛んだときに歯が浮いたような違和感が現れます。さらに歯槽骨の吸収が進めば、歯が動揺して噛むたびに痛みを伴うようになるのです。
このように、虫歯は神経を直接刺激することで強い痛みを引き起こし、歯周病は炎症や組織の破壊によってじわじわと痛みが現れるという違いがあります。
セルフチェックのポイント
虫歯と歯周病は痛みの出方が異なるため、ご自身でチェックできるサインも違います。虫歯の場合は「冷たいものや甘いものがしみる」「噛んだときにズキッと痛む」といった感覚が代表的です。鏡で確認すると、歯の表面が白く濁っていたり黒ずんでいたり、小さな穴が見えることもあります。これらの変化は早期に治療を始めるべきサインといえます。
一方、歯周病では初期に強い痛みが出ないため、歯ぐきの変化を見逃さないことが大切です。「歯磨きの際に血が出る」「歯ぐきが赤く腫れている」「口臭が気になる」といった症状があれば要注意です。さらに進行すると、歯がぐらついたり、歯ぐきが下がって歯が長く見えるといった変化が出てきます。
このようなセルフチェックで異常に気づいた場合は、早めに歯科医院を受診することが重要です。とくに歯周病は自覚症状が乏しく静かに進むため、定期検診を受けて専門的に診てもらうことが予防の第一歩となります。
予防法の違いと共通点

虫歯と歯周病は発症の仕組みが異なるものの、どちらも毎日のセルフケアと定期的な歯科受診が欠かせません。虫歯は「糖の摂取頻度」と「歯の再石灰化」が予防の鍵であり、フッ素の活用や間食の管理が有効です。一方、歯周病はプラークと歯石の蓄積が主な原因であるため、歯磨きの方法を工夫し、定期的に歯石を取り除くことが重要になります。
ただし両者に共通して言えるのは、毎日の正しいブラッシングと生活習慣の改善、そして歯科医院での定期的なチェックによって予防効果が大きく高まるということです。次では、虫歯予防・歯周病予防・共通の基本についてそれぞれ詳しく解説します。
虫歯予防
虫歯を防ぐために最も重要なのは、細菌が作り出す酸から歯を守ることです。日常生活では、糖分を含む飲食物をだらだらと摂取しないように心がけ、間食や甘い飲み物の回数を減らすことが大切です。また、フッ素入りの歯磨き粉を毎日使用することで歯の再石灰化を促し、初期虫歯の進行を抑える効果が期待できます。さらに、定期的に歯科医院でフッ素塗布やフッ素洗口を取り入れると、歯質を強化して虫歯になりにくい状態を維持できます。
のだ歯科クリニックでは、オラブリスやビーブランドといったフッ素洗口の導入を積極的に行い、患者様の年齢や生活習慣に合わせた予防プランを提案しています。ご家庭でのセルフケアと歯科医院での専門的なサポートを組み合わせることが、虫歯予防の基本であり、長期的に自分の歯を守るための近道なのです。
歯周病予防
歯周病の予防で最も重要なのは、歯と歯ぐきの境目にたまるプラークや歯石を取り除き、細菌の温床を作らないことです。毎日の歯磨きでは、歯ブラシだけでなくデンタルフロスや歯間ブラシを使い、細かい部分まで丁寧に清掃することが欠かせません。しかしセルフケアだけでは限界があるため、定期的に歯科医院で歯石を除去し、歯周ポケット内のクリーニングを受けることが大切です。
のだ歯科クリニックでは、従来の超音波スケーラーだけでなく、エアフローを用いた歯面清掃を取り入れています。微細なパウダーと水流で歯面や歯周ポケット内のバイオフィルムを効果的に除去でき、従来よりも快適で短時間にケアが可能です。また、ポイックウォーターによる殺菌や口腔内環境の改善も組み合わせ、歯周病の再発を防ぐ取り組みを徹底しています。こうしたプロのサポートと日々のセルフケアを継続することが、歯周病予防の基本といえるのです。
共通する予防の基本
虫歯と歯周病はいずれも生活習慣病の一種であり、毎日のセルフケアと歯科医院での定期管理を組み合わせることが最大の予防策です。まず欠かせないのは、正しいブラッシング習慣です。歯並びや年齢に合わせた清掃方法を身につけ、フッ素入り歯磨き粉を継続的に使用することで、歯質強化と細菌抑制の両方を実現できます。
また、3〜6か月ごとの定期健診でプロによるチェックを受け、早期発見・早期治療につなげることが重要です。のだ歯科クリニックでは担当衛生士制を採用し、一人ひとりの生活背景に応じた予防プログラムを提案しています。加えて、リポCによるビタミンC補給やクリアコーティングFによる歯質強化など、全身と口腔をトータルで考えたサポートも行っています。こうした日常の工夫と専門的なケアの両立が、長く健康な歯を維持するための共通した基本となるのです。
のだ歯科クリニックの診療方針
のだ歯科クリニックでは、「できるだけ歯を残す」ことを基本に、患者様一人ひとりに合わせた治療を行っています。虫歯や歯周病は放置すれば歯を失う大きな原因となりますが、当院では歯科用CTや拡大鏡・マイクロスコープを用いた精密な診断により、保存できる歯を丁寧に見極めます。また、女性医師を含む体制で幅広いニーズに対応し、患者様が安心して相談できる環境を整えています。
さらに、担当衛生士制を導入し、長期的にお口の健康を見守るサポート体制を構築。定期的なメンテナンスでは、エアフローによるバイオフィルム除去やフッ素洗口、ポイックウォーターを活用し、再発防止と予防にも力を注いでいます。ビタミンC(リポC)による全身的な健康サポートや、クリアコーティングFによる知覚過敏改善・歯質強化なども積極的に取り入れ、総合的なアプローチで患者様を支えています。
次では、具体的に当院の診療方針を「歯を残す治療」「精密診断」「長期管理」「安心できる環境づくり」という観点からご紹介します。
できるだけ歯を抜かずに治療
のだ歯科クリニックでは、「歯を残すこと」に強いこだわりを持っています。虫歯や歯周病が進行している場合でも、すぐに抜歯を選択するのではなく、まずは精密な診査診断を行い、本当に保存が不可能かを慎重に見極めます。歯科用CTや拡大鏡・マイクロスコープを活用して歯の状態を詳細に確認し、根管治療や歯周治療など、可能な限り歯を残すための方法を提案します。
歯を抜くと、噛み合わせのバランスが崩れたり、見た目や発音に影響が出たりするだけでなく、インプラントや入れ歯など大きな治療が必要になることも少なくありません。だからこそ、天然の歯を守ることは、患者様の将来の生活の質を保つうえで非常に大切なのです。当院では「抜かない努力」を基本に、患者様が長く自分の歯で快適に過ごせるようサポートしています。
精密診断(CT・拡大鏡・マイクロスコープ)による原因究明
のだ歯科クリニックでは、病気の本質を正しく捉えるために、歯科用CT・拡大鏡・マイクロスコープを駆使した精密診断を行っています。虫歯や歯周病は、肉眼では確認が難しい部分に潜んでいることが多く、従来のレントゲンだけでは見落としが生じる可能性があります。CTを用いることで歯や骨の状態を立体的に把握でき、病変の広がりや骨の吸収状態を正確に評価できます。
また、拡大鏡やマイクロスコープを活用することで、わずかな虫歯の取り残しや細部の歯石まで鮮明に確認することができ、治療の精度を飛躍的に高めることが可能です。視野を拡大することで、必要最小限の処置で歯を守ることにもつながります。
当院では、このような「精密な見極め」を重視し、診断結果を丁寧にご説明しながら、患者様にとって最適な治療方針をご提案しています。原因を的確に突き止めることこそが、再発を防ぎ、歯を長持ちさせる第一歩なのです。
担当衛生士制での長期管理
のだ歯科クリニックでは、治療の一時的な改善にとどまらず、患者様が将来にわたって健康な口腔環境を維持できるよう「担当衛生士制」を導入しています。毎回同じ衛生士が経過を見守ることで、生活習慣やセルフケアの癖、歯ぐきの変化を細かく把握し、きめ細やかなサポートが可能になります。
定期的なメンテナンスでは、歯石除去やクリーニングに加え、エアフローによるバイオフィルム除去やポイックウォーターでの口腔環境改善を行い、再発を防ぐ体制を整えています。また、フッ素洗口やビタミンC(リポC)の摂取など、全身の健康も考慮した予防プログラムを提案しています。
こうした長期的な視点に基づく管理により、患者様は「治療して終わり」ではなく、「一生自分の歯で噛める未来」を目指すことができます。担当衛生士と二人三脚で進める継続的なケアこそが、歯を守るための最も確実な方法なのです。
安心して通える環境づくり
のだ歯科クリニックでは、患者様が安心して通院できる環境づくりを大切にしています。歯科治療は「痛い」「怖い」というイメージを持たれることが多いため、当院では丁寧なカウンセリングを行い、不安や疑問を一つひとつ解消してから治療に進むよう心がけています。治療内容や進行状況は写真や画像を使ってわかりやすく説明し、納得していただいたうえで治療を選択できる体制を整えています。
また、女性医師を含む体制で幅広いニーズに応えられることも当院の特徴です。小さなお子様からご高齢の方まで、家族で安心して通える総合歯科として、一般歯科から小児・矯正・インプラントまで幅広く対応しています。さらに院内は清潔で快適な空間づくりに配慮し、滅菌体制や感染予防も徹底しています。
「ここなら安心して通える」と感じていただける環境を整えることで、患者様が治療を継続しやすくなり、結果として健康な歯を長く守ることにつながります。
まとめ:虫歯と歯周病の違いを正しく理解して予防・治療を

虫歯と歯周病は、いずれも歯を失う大きな原因でありながら、発症の仕組みや症状の現れ方には明確な違いがあります。虫歯は早期から痛みを伴いやすく、歯そのものを溶かしていく病気です。一方、歯周病は痛みが少ないまま進行し、歯を支える歯ぐきや骨を破壊していく病気であり、気づいたときには重度化していることも少なくありません。
いずれも放置すれば生活の質を大きく損ない、最終的には歯を失うリスクを避けられません。そのため、正しい知識を持ち、日常のケアと定期的な歯科検診を継続することが最も大切です。
のだ歯科クリニックでは「できるだけ歯を抜かずに残す」という方針のもと、精密診断と丁寧な治療、そして担当衛生士による長期的なサポートを行っています。放置のリスクを避け、安心して治療を受けたい方は、ぜひ当院にご相談ください。
関連記事
2026.01.14
部分入れ歯ができるまでの仮歯(仮入れ歯)とは|歯がない期間をどう過ごす?
2025.12.31
ホワイトニングがめちゃくちゃ痛い…寝れない原因と対処法|歯医者に行く目安も解説
2025.12.26
ホワイトニングは歯医者とサロンどっち?歯医者の方がいい理由・違い・値段・後悔しない選び方
2025.12.19