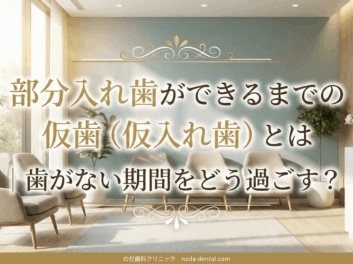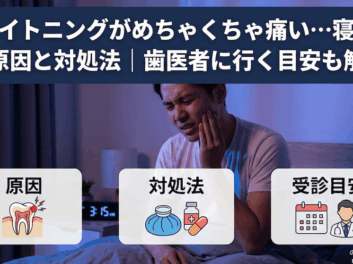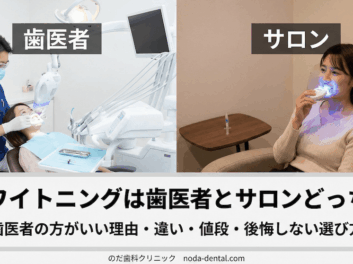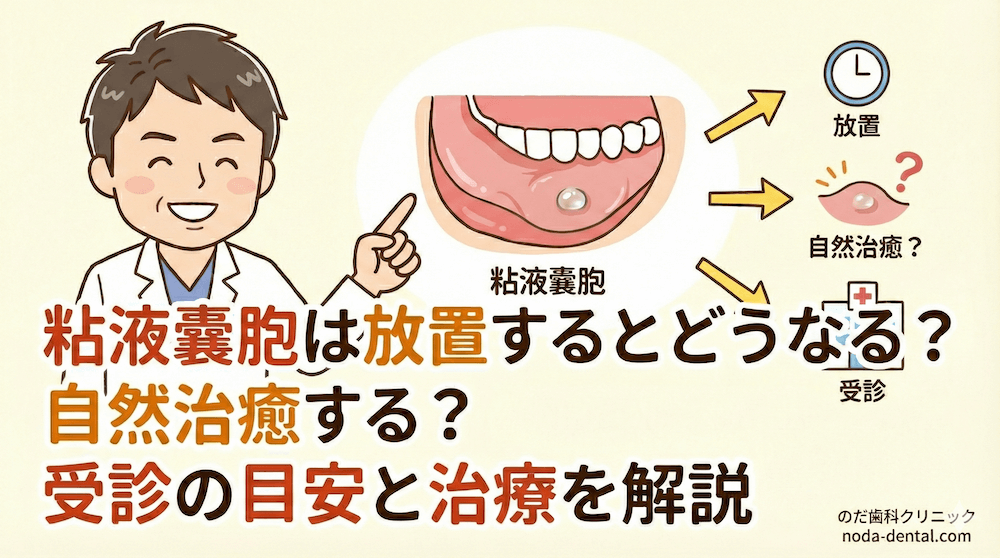歯周病で食べてはいけないもの|悪化を防ぐ食事と注意点
2025.09.07

「歯周病と診断されたけれど、具体的にどのような食べ物を避ければよいのか分からない」と不安を抱えている方は少なくありません。実際に、食生活は歯周病の進行や予防に大きく関わっており、毎日の選択によって口腔環境が悪化することもあれば、逆に改善に役立つこともあるのです。
本記事では、歯周病の方が食べてはいけない食品とその理由、歯ぐきを守るために積極的に摂りたい食品や食習慣について詳しく解説します。また、歯周病を進行させないために欠かせないセルフケアや歯科医院での治療についてもご紹介します。
当院・のだ歯科クリニックでは、「できるだけ歯を抜かずに守る治療」を基本方針とし、精密な診査診断と丁寧なケアを行っています。担当衛生士制を導入しているため、一人ひとりに合わせた継続的なサポートが可能です。さらに、痛みに配慮した治療を心がけておりますので、安心してご相談いただけます。
歯周病と食べ物の関係

歯周病は細菌によって引き起こされる炎症性の病気ですが、実は食生活もその進行や予防に大きく影響します。毎日の食事の内容や食べ方によって、口の中の細菌が活発になることもあれば、逆に細菌の増殖を抑えることもあるのです。つまり、歯周病は「歯磨きや通院だけでなく、食事選び」も大切な予防要素になるといえます。
特に糖分や酸の多い食品はプラーク(歯垢)の栄養源となり、歯周病菌が増殖する原因になります。また、硬い食べ物で歯ぐきに負担をかけると炎症を悪化させる恐れもあります。一方で、ビタミンやカルシウムを多く含む食品は歯や歯ぐきを健康に保つ働きがあり、食生活が整うことで歯周病の進行を抑える助けとなります。
このように、食べ物は「歯周病が悪化する要因」と「歯ぐきを守る味方」の両面を持っています。以下では、まず歯周病がどのように悪化するのか、そしてなぜ食べ物が大きく影響するのかを解説していきましょう。
歯周病が悪化する仕組み
歯周病は、口の中に存在する細菌が歯と歯ぐきの境目にたまり、炎症を引き起こすことから始まります。プラークと呼ばれる細菌のかたまりが増えると、歯ぐきが赤く腫れたり出血したりする「歯肉炎」の状態になります。これを放置すると炎症が深部へ進行し、歯を支える骨が溶けていく「歯周炎」へと進んでいくのです。
炎症が続くことで免疫力が低下し、細菌に対する防御力も弱まります。その結果、歯周ポケット(歯と歯ぐきの隙間)が深くなり、さらに細菌がたまりやすい環境がつくられてしまいます。悪循環に入ると炎症が広がり、最終的には歯がぐらつき、抜け落ちてしまうリスクが高まります。
このような仕組みを理解すると、歯周病は「ただの歯ぐきの腫れ」ではなく、全身の健康にも関わる病気であることが分かります。特に食べ物の選び方や生活習慣が炎症の悪化に影響を与えるため、日常の心がけがとても重要なのです。
なぜ食べ物が影響するのか
歯周病の進行に食べ物が深く関わるのは、口の中にいる細菌が「食べかすや糖分」を栄養源として繁殖するためです。特に砂糖を多く含むお菓子や清涼飲料水は、細菌の活動を活発にし、プラークを増やす大きな原因となります。プラークが蓄積すると歯石へと硬化し、歯ブラシでは取り除けなくなり、歯周病を悪化させる温床となるのです。
また、酸性の強い飲み物(炭酸飲料やアルコールなど)は、歯や歯ぐきの表面を刺激して炎症を助長します。こうした刺激は歯肉の抵抗力を弱め、歯周ポケットの悪化につながります。さらに、栄養の偏った食事は体全体の免疫力を低下させ、歯周病菌に対抗する力を奪ってしまいます。
逆に、栄養バランスの取れた食事は歯や歯ぐきの修復力を高め、歯周病の進行を抑える助けとなります。つまり、食事は単なるエネルギー補給ではなく、「歯周病の悪化と予防を分ける大きな要因」になるのです。
歯周病の人が食べてはいけないもの
歯周病の進行を抑えるためには、毎日の食生活を見直すことが欠かせません。特に、歯ぐきや歯周ポケットに悪影響を及ぼす食品を避けることは、治療と並行して非常に重要です。甘いお菓子や清涼飲料水などの糖分は、プラークの栄養源となって歯周病菌を活発化させます。さらに、硬い食品は歯ぐきに物理的な負担をかけ、炎症部位を悪化させる可能性があります。また、酸性の強い飲み物は歯肉や歯の表面を刺激し、炎症を助長する要因となります。
つまり、「何を食べるか」によって歯周病の進行度は大きく左右されるのです。ここからは、特に注意すべき食品群を具体的に解説していきます。
砂糖・甘いもの

歯周病の方にとって最も注意が必要なのが、砂糖を多く含む食品です。チョコレートやキャンディー、ケーキなどの菓子類はもちろん、清涼飲料水や缶コーヒーにも大量の糖分が含まれています。これらを摂取すると、口の中に残った糖分が歯周病菌を含むプラークの栄養源となり、細菌の繁殖を急速に進めてしまいます。
さらに、砂糖は歯を溶かす酸をつくり出す原因にもなるため、歯周病の進行と同時に虫歯リスクも高めます。特に間食やだらだらとした飲食習慣は、口腔内が常に糖分にさらされる状態を生み、炎症を悪化させる大きな要因になります。
そのため、甘いものを完全に避けるのが難しい場合でも、摂取する頻度を減らし、食べたあとはしっかり歯磨きやうがいを行うことが大切です。
硬い食べ物

せんべいやナッツ類などの硬い食べ物は、歯周病の方にとって注意が必要です。炎症で弱っている歯ぐきや歯を支える骨に強い力がかかると、歯の動揺が悪化したり、歯ぐきに傷をつけて炎症をさらに進めてしまう恐れがあります。特に奥歯で硬い食材を噛むと、歯周ポケットの内部に負担がかかり、出血や腫れを繰り返すことにつながりやすいのです。
また、ナッツやポップコーンの皮などは細かい破片が歯と歯ぐきの隙間に入り込みやすく、取り除きにくいため、炎症の温床となります。こうした食品は健康な状態であれば栄養価の高い食材ですが、歯周病が進行している方にはリスクが大きいといえるでしょう。
どうしても硬い食品を口にする場合は、量を控えたり、細かく砕いてから食べるなどの工夫が必要です。炎症が治まるまではできるだけ避け、歯ぐきに負担をかけない食事を心がけることが大切です。
酸性の強い飲み物

炭酸飲料、コーヒー、アルコールなどの酸性度が高い飲み物は、歯周病を悪化させる要因の一つです。これらの飲み物は口の中を酸性環境に傾け、歯や歯ぐきの表面を刺激します。炎症が起きている歯肉にとって酸は大きな負担となり、赤みや腫れをさらに悪化させることがあります。
また、酸性飲料は歯の表面を溶かす「酸蝕(さんしょく)」を引き起こしやすく、歯周病と同時に歯の弱体化を招くリスクがあります。特に炭酸飲料やエナジードリンクは糖分も多く含まれているため、プラークの繁殖を助長し、二重の悪影響を及ぼします。
日常的に酸性飲料を摂っていると、歯周病治療を行っていても炎症が治まりにくくなることがあります。完全に避けるのが難しい場合は、ストローを使って歯や歯ぐきに直接触れないようにしたり、飲んだ後に水で口をすすぐなどの工夫を取り入れることが望ましいでしょう。
歯周病予防に良い食べ物
歯周病は「避けるべき食品」に注意することも大切ですが、同時に「積極的に摂りたい食品」を意識することで、歯ぐきや歯を健康に保つサポートができます。栄養バランスの良い食事は体全体の免疫力を高めるとともに、炎症を抑え、歯周病の進行を防ぐ効果が期待できるのです。
特にビタミンCやビタミンEは歯ぐきの修復や抗酸化作用に役立ちますし、カルシウムやタンパク質は歯や骨を強く保つために欠かせません。また、よく噛むことで唾液分泌を促す繊維質の食品は、口の中を清潔に保ち、細菌の繁殖を抑える働きを持っています。
このように、食生活の工夫は歯周病治療の一環として重要です。ここからは、歯周病予防に役立つ代表的な食品群について詳しくご紹介します。
ビタミンC・Eを含む食品
歯周病の予防や改善には、ビタミンCとビタミンEを積極的に摂取することが推奨されます。ビタミンCはコラーゲンの生成を助け、歯ぐきの修復や強化に欠かせない栄養素です。不足すると歯肉がもろくなり、出血しやすくなるため、歯周病の悪化を防ぐためには特に重要といえます。柑橘類やイチゴ、キウイ、パプリカ、ブロッコリーなどに豊富に含まれています。
一方、ビタミンEは強力な抗酸化作用を持ち、細胞の老化を防ぎながら血行を促進する働きがあります。これにより歯ぐきの炎症を抑え、健康な状態を保ちやすくなるのです。アーモンドやひまわり油、ほうれん草、アボカドなどが代表的な食品です。
これらの栄養素を日常的に摂ることで、歯周病治療の効果を高め、歯ぐきの回復をサポートすることができます。サプリメントに頼るのではなく、できる限り食事から自然に取り入れることが理想的です。
カルシウム・タンパク質を含む食品
歯周病の進行を防ぐためには、歯や歯を支える骨を強く保つことが欠かせません。そのために重要な栄養素がカルシウムとタンパク質です。カルシウムは歯や骨の主要な成分であり、不足すると歯を支える力が弱まり、歯の動揺や喪失リスクを高めてしまいます。牛乳やヨーグルト、チーズなどの乳製品、小魚や海藻類には豊富なカルシウムが含まれています。
また、タンパク質は筋肉や骨だけでなく、歯ぐきの組織を修復する材料にもなります。肉、魚、大豆製品、卵などに多く含まれており、歯周病の炎症が起きた組織の回復をサポートします。特に魚はカルシウムとタンパク質の両方をバランスよく含むため、日常的に取り入れると良いでしょう。
カルシウムとタンパク質を意識して摂取することで、歯そのものだけでなく、歯を支える歯槽骨や歯ぐきの健康を守ることができます。歯周病の方にとって、これらの栄養素は「治療の基盤」となる大切な存在なのです。
よく噛める繊維質の食品
野菜や海藻などの繊維質を多く含む食品は、歯周病予防に大きな役割を果たします。繊維質の食材はしっかり噛む必要があるため、自然と咀嚼回数が増え、唾液の分泌を促します。唾液には口の中を洗浄し、細菌の繁殖を抑える作用があるため、歯周病のリスクを軽減する効果が期待できるのです。
また、食物繊維は腸内環境を整える働きもあり、免疫力を高めて歯ぐきの炎症を抑えるサポートにつながります。ごぼうやにんじん、キャベツ、わかめ、ひじきなどは日常的に取り入れやすく、歯周病予防の観点からもおすすめできる食品です。
繊維質の食品は、単に栄養面で優れているだけでなく、「よく噛む習慣」をつくることができる点でも価値があります。早食いを避け、時間をかけて噛むことで、歯や歯ぐきに適度な刺激が加わり、健康な口腔環境を保ちやすくなるのです。
食生活で注意したい習慣

歯周病を予防・改善するためには、特定の食品を避けたり摂取したりするだけでなく、日々の「食べ方」や「生活習慣」にも気を配ることが大切です。どれほど栄養バランスに優れた食事をしていても、間食が多かったり、早食いの習慣があったりすると、口腔環境は乱れやすくなります。また、食後のケアを怠ると、プラークが残って歯周病の悪化につながってしまうのです。
歯周病は慢性的に進行する病気であるため、生活習慣の積み重ねが予防のカギを握っています。特に「間食の頻度」「咀嚼の仕方」「食後のケア」は、日常的に意識するだけでも大きな違いを生み出すポイントです。
ここからは、歯周病の方が日常生活で注意すべき具体的な習慣についてご紹介します。
間食の回数を減らす
間食が多い生活は、歯周病を悪化させる大きな要因のひとつです。お菓子や甘い飲み物を少しずつ何度も口にすると、口腔内が常に糖分にさらされた状態になり、プラークが作られやすくなります。これにより細菌が繁殖し、歯ぐきの炎症が治まりにくくなってしまうのです。
また、食事の回数が増えると、唾液による自然な自浄作用が追いつかなくなり、口腔環境が悪化しやすくなります。特に夜遅くの間食は唾液分泌が少ないため、細菌にとって理想的な繁殖環境を与えてしまいます。
完全に間食をやめるのが難しい場合は、決まった時間に少量だけ摂るようにし、食後には水で口をすすぐか軽く歯磨きを行うことをおすすめします。こうした工夫を取り入れることで、歯周病の進行を抑える効果が期待できます。
よく噛む・早食いを避ける
早食いの習慣は、歯周病にとって望ましくありません。食べ物をよく噛まずに飲み込むと、唾液の分泌が十分に促されず、口の中を洗い流す作用や殺菌作用が弱まってしまいます。その結果、プラークがたまりやすくなり、歯周病の悪化につながるのです。
一方で、よく噛む習慣を身につけると、唾液の分泌量が増え、口腔内が清潔に保たれやすくなります。さらに、唾液には歯や歯ぐきを修復する成分も含まれているため、歯周病予防の大きな助けとなります。
また、ゆっくり噛んで食べることで食事の満足感が高まり、間食を減らす効果も期待できます。日常生活の中で「一口につき20回以上噛む」「急いで食べない」といった意識を持つことが、歯ぐきの健康を守る第一歩になるのです。
食後の歯磨き・うがい
食後に口の中を清潔に保つことは、歯周病の予防に欠かせません。食事をするとプラークのもととなる糖分や食べかすが歯の表面に付着し、細菌の活動が活発になります。そのまま放置すると炎症が悪化し、歯周病の進行を早めてしまうのです。
基本は、食後に歯磨きを行い、歯と歯ぐきの境目を丁寧に清掃することが重要です。外出先などで歯磨きが難しい場合には、最低限、水やお茶で口をすすぐだけでも効果があります。これにより食べかすや酸を洗い流し、口腔内環境を整えることができます。
特に就寝前は唾液の分泌量が減るため、細菌が繁殖しやすい状態になります。そのため、夜の歯磨きは一日の中でも最も丁寧に行うことが推奨されます。日々の小さな習慣の積み重ねが、歯周病の進行を防ぎ、健康な歯ぐきを守ることにつながるのです。
歯周病のセルフケアと歯科での治療

歯周病を改善・予防するためには、食生活の見直しだけでなく、セルフケアと歯科医院での専門的な治療を組み合わせることが欠かせません。歯周病は慢性的に進行する病気であり、毎日の歯磨きやフロスといった習慣的なケアと、歯科医による専門的な処置を継続して行うことで、はじめてコントロールが可能になるのです。
セルフケアでは、歯ブラシでの磨き残しを減らすことに加え、フロスやマウスウォッシュを活用することで、歯と歯の隙間や歯周ポケットの汚れを効果的に取り除けます。しかし、自宅でのケアだけでは完全にプラークや歯石を除去することは難しく、定期的に歯科医院でのクリーニングや検査を受けることが重要です。
当院でも、歯周病の進行度に応じてスケーリングや歯周外科治療などの専門的な処置を行い、患者様一人ひとりに合わせた治療計画を立てています。セルフケアと歯科での治療を両立させることが、歯周病を悪化させない最も確実な方法といえるでしょう。
セルフケア(歯磨き・フロス・マウスウォッシュ)
歯周病の進行を抑えるためには、毎日のセルフケアが欠かせません。まず基本となるのは、歯ブラシによる丁寧なブラッシングです。歯と歯ぐきの境目に毛先を当て、小刻みに動かしながら磨くことで、プラークを効果的に取り除くことができます。力を入れすぎると歯ぐきを傷つけてしまうため、優しいタッチを心がけることが大切です。
さらに、歯ブラシだけでは落としきれない歯と歯の間の汚れは、デンタルフロスを活用することで清掃できます。フロスは虫歯予防だけでなく、歯周病の原因となるプラークを除去するうえでも有効です。加えて、マウスウォッシュを併用すると、口腔内全体の細菌数を減らし、炎症のコントロールに役立ちます。
このように、歯磨き・フロス・マウスウォッシュを組み合わせたセルフケアは、歯周病予防の基本であり、日常生活に欠かせない習慣です。継続して取り入れることで、歯科医院での治療効果も高まりやすくなります。
歯科医院での治療(スケーリング・歯周外科)
歯周病はセルフケアだけでは完全にコントロールできないため、歯科医院での専門的な治療が欠かせません。特に歯石は一度付着すると歯ブラシでは落とせず、専用の器具を用いた「スケーリング」によって除去する必要があります。スケーリングを行うことで、歯周病菌の温床となる歯石を取り除き、歯ぐきの炎症を改善へと導きます。
進行が進んでいる場合には、「ルートプレーニング」と呼ばれる処置で歯の根の表面を滑らかにし、細菌の再付着を防ぎます。それでも改善が見られない重度の歯周病では、歯周外科治療が検討されることもあります。歯ぐきを一部切開して歯根を直接清掃することで、深い歯周ポケットに潜む細菌を徹底的に除去できるのです。
このように、歯科医院での治療は歯周病の進行度に応じて段階的に行われます。定期的なメンテナンスと併せて受診することで、歯を長く健康に保つことが可能となります。
のだ歯科クリニックの歯周病治療の特徴
歯周病治療は「どの歯科医院で受けるか」によって、その後の経過や満足度が大きく変わります。当院・のだ歯科クリニックでは、患者様の歯をできるだけ長く残すことを目指し、精密な診断と継続的なサポートを重視しています。歯周病は生活習慣病の一つともいわれ、治療を一度受けて終わりではなく、定期的なケアとフォローが欠かせません。当院ではその点を踏まえ、患者様に安心して治療を継続いただける体制を整えております。
具体的には、安易に抜歯をせずに「残せる歯を見極めて守る治療方針」、患者様一人ひとりを担当する「衛生士制による長期的ケア」、さらに「女性医師による丁寧で柔軟な対応」を特徴としています。これにより、患者様の不安を和らげながら、生活背景やご希望に合わせた治療をご提案することが可能です。
ここからは、当院の歯周病治療における具体的な強みについて詳しくご紹介します。
できるだけ抜歯を避ける治療
のだ歯科クリニックでは、「なるべく歯を残す」ことを基本方針としています。歯周病が進行すると、歯ぐきや骨のダメージから抜歯を勧められるケースもありますが、当院では安易に抜歯を選択することはありません。精密な診査・診断を行い、残せる可能性がある歯については最大限保存できるよう努めています。
そのために、歯科用CTや拡大鏡といった精密機器を駆使し、歯や歯ぐきの状態を細かく確認します。歯の動揺や骨の吸収の程度を正確に把握することで、患者様にとって最適な治療法を選択できるのです。
「歯を失いたくない」というお気持ちは、多くの患者様が共通して抱えているものです。当院はその思いに寄り添い、できる限り歯を保存する治療を提案しています。
担当衛生士制による継続的ケア
歯周病は一度治療を受ければ終わりではなく、継続的な管理が欠かせない病気です。そのため当院では、患者様ごとに担当の歯科衛生士を配置し、長期的なサポート体制を整えています。
担当衛生士が一貫してケアを行うことで、毎回の口腔内の変化を細かく把握でき、的確な指導や処置を行うことが可能になります。例えば、ブラッシングの癖や磨き残しの傾向を継続的にチェックし、患者様一人ひとりに合わせた改善方法をご提案します。
また、定期検診のたびに担当者が変わらないため、患者様にとって安心感があり、信頼関係を築きやすいことも大きなメリットです。歯周病治療は時間をかけて取り組む必要があるからこそ、伴走者としての衛生士の存在が重要なのです。
精密診断と丁寧な説明による安心感
のだ歯科クリニックでは、歯科用CTやマイクロスコープ、拡大鏡といった精密機器を積極的に導入し、歯や歯ぐきの状態を細部まで正確に把握しています。肉眼だけでは見落とされやすい小さな異変も確認できるため、治療の精度が高まり、歯をできる限り残す診療につながります。特に歯周病は進行度の見極めが重要な病気であり、こうした精密診断によって患者様に合った最適な治療計画を立案することが可能となるのです。
また、診療の前後には撮影した画像や模型を用い、わかりやすい言葉で丁寧に説明を行っています。歯周病治療は長期的な通院が必要となることも多く、患者様がご自身の状態を理解し、納得して治療を進めていただくことがとても大切です。「なぜこの治療が必要なのか」「どのような効果が期待できるのか」を明確にすることで、不安や疑問を解消し、安心して診療に臨んでいただけます。
当院では、精密な診断と誠実な説明を徹底することで、患者様が納得感を持ちながら治療に取り組める環境を整えています。単に技術的な処置を行うだけでなく、「理解」と「安心」を重視する姿勢こそが、歯周病治療を長く継続していくうえで大きな支えとなるのです。
まとめ:歯周病を悪化させないために食事と治療を見直しましょう

歯周病は生活習慣病のひとつであり、毎日の食事内容が進行や改善に大きく関わります。砂糖を多く含むお菓子や清涼飲料水、硬い食品や酸性の強い飲み物は、歯茎や歯周組織に負担を与え、炎症の悪化につながるため注意が必要です。一方で、ビタミンCやEを含む野菜・果物、カルシウムやタンパク質を含む魚や乳製品、よく噛むことができる繊維質の食品は、歯茎の健康維持や免疫力向上に役立ちます。
しかし、食生活だけで歯周病を完全に防ぐことはできません。セルフケアや歯科医院での定期的なクリーニング・精密診断を組み合わせることが、歯を長く守るために欠かせません。
のだ歯科クリニックでは、「できるだけ抜歯を避ける治療」「担当衛生士制による継続的ケア」「精密診断と丁寧な説明による安心感」を大切にしています。歯周病を放置すると歯を失うリスクが高まりますが、適切な対応をとれば進行を止めることも可能です。食事と治療の両面から歯周病を予防し、健康な口腔環境を保ちたい方は、ぜひ一度当院へご相談ください。
関連記事
2026.01.14
部分入れ歯ができるまでの仮歯(仮入れ歯)とは|歯がない期間をどう過ごす?
2025.12.31
ホワイトニングがめちゃくちゃ痛い…寝れない原因と対処法|歯医者に行く目安も解説
2025.12.26
ホワイトニングは歯医者とサロンどっち?歯医者の方がいい理由・違い・値段・後悔しない選び方
2025.12.19