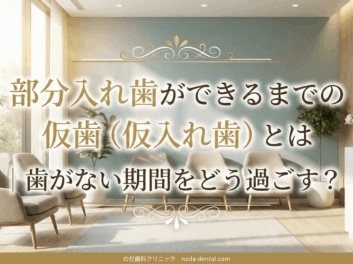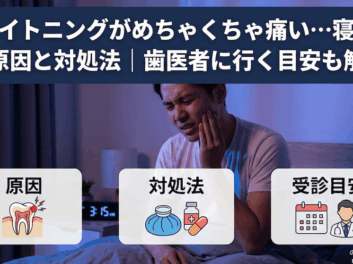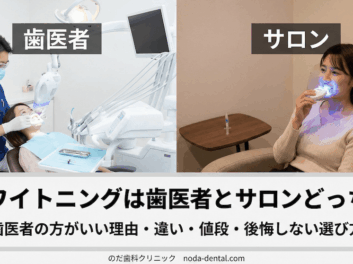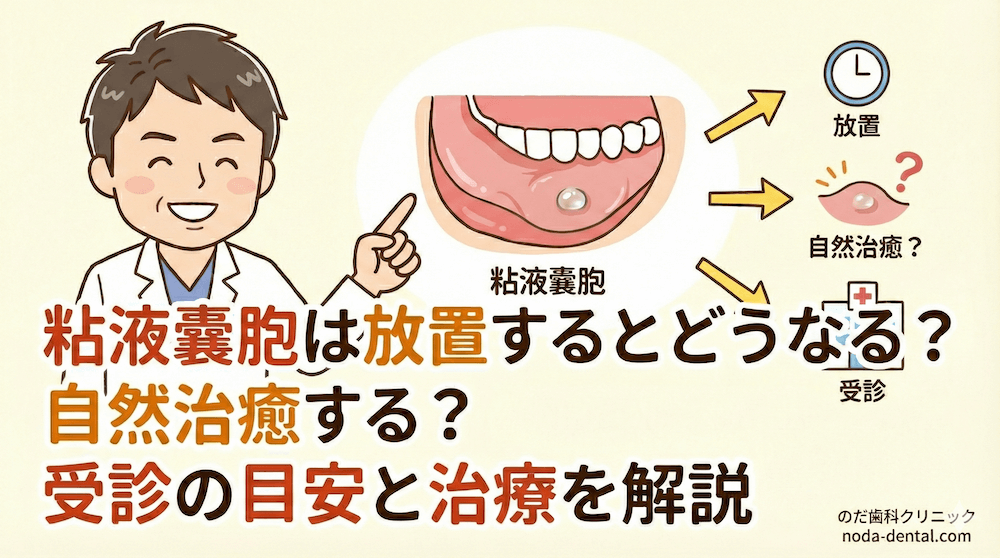インプラントの抜糸はいつ?痛み・腫れ・注意点を解説|一次・二次手術での違いも紹介
2025.10.05

インプラント手術を受けた後、「抜糸のタイミングはいつ?」「痛みはあるの?」と不安に感じる方は少なくありません。抜糸は、手術で縫合した糸を取り除き、傷の治りを促す大切な処置です。通常は10分ほどで終わる簡単な処置ですが、適切な時期を逃すと炎症や腫れの原因となることもあります。特に一次手術と二次手術では抜糸のタイミングや注意点が異なるため、医師の指示に従うことが重要です。
本記事では、インプラントの抜糸に関する正しい知識を、痛み・腫れ・生活上の注意点を交えながらわかりやすく解説します。また、抜糸後のトラブルを防ぐための過ごし方や、吸収性糸を使用した場合の対応についても紹介します。術後の経過を安心して過ごせるよう、信頼できる歯科医院でのフォローアップの大切さもお伝えします。
インプラントの「抜糸」とは:目的と基本の流れ

インプラント手術では、歯ぐきを切開して顎の骨にインプラント体を埋め込み、その後に歯ぐきを縫い合わせて保護します。抜糸とは、その縫合糸を取り除く処置のことで、治療の流れの中では「傷の治りを確認する重要な節目」にあたります。
糸を取り除く目的は、創部の感染予防と治癒の促進、そして異物感の解消です。縫合糸を長く残したままにすると、細菌が付着しやすくなり、炎症や腫れ、場合によっては再感染を招くこともあります。
抜糸自体は麻酔を必要としない簡単な処置で、所要時間は10分程度が目安です。処置後は痛みもほとんどなく、当日から食事が可能なケースも多く見られます。ただし、治癒経過や体調によっては、医師が抜糸の時期を調整することもあります。
ここからは、「なぜ抜糸が必要なのか」「糸の種類による違い」など、具体的なポイントを順に解説していきます。
なぜ抜糸が必要なのか
インプラント手術後の抜糸は、創部を清潔に保ち、スムーズな治癒を促すために欠かせない工程です。手術時に使用する縫合糸は、歯ぐきを安定させて出血や感染を防ぐ役割を持っていますが、役目を終えた後も長く残しておくと、そこに細菌が付着して炎症の原因となることがあります。
また、糸が残ったままだと食べかすや汚れが絡まりやすく、傷口の治りを妨げてしまうこともあります。特にインプラント周囲の歯ぐきは、手術後にまだデリケートな状態にあるため、不要な刺激や細菌の繁殖を防ぐことが大切です。
抜糸を行うことで、こうした感染リスクを減らし、歯ぐきが自然に再生していく環境を整えることができます。結果として、腫れや痛みの回復が早まり、インプラント全体の治療経過にも良い影響を与えるのです。
縫合糸の種類と特徴(吸収性・非吸収性)
インプラント手術で使用される縫合糸には、「吸収性」と「非吸収性」の2種類があります。それぞれに特徴と適した使い方があり、手術の内容や創部の状態に応じて選択されます。
吸収性の糸は、体内の酵素反応によって自然に溶けていく素材で作られており、一般的には2〜3週間ほどで吸収されます。抜糸の必要がないため、患者様の負担が少なく済みますが、体質や治癒経過によっては一部が残る場合があり、その際は来院して除去することもあります。
一方、非吸収性の糸は体内で分解されないため、治癒が進んだ段階で歯科医院で取り除く必要があります。外科処置後の創部をしっかり固定できるため、安定性が高く、感染リスクを抑える目的で選ばれることもあります。
どちらの糸も適切な管理と時期を守ることで、傷の治りを助け、トラブルを防ぐことができます。
抜糸の時期はいつ?一般的な目安と個人差

インプラントの抜糸は、手術からおよそ7〜10日後に行うのが一般的です。これは、歯ぐきの傷口がある程度ふさがり、縫合糸の役割が終わる時期にあたるためです。早すぎると創部が開いてしまうおそれがあり、逆に遅れると細菌の付着や炎症が起こりやすくなります。そのため、最適なタイミングで抜糸を行うことが治癒促進の鍵となります。
ただし、抜糸の時期には個人差があります。年齢や体質、全身疾患の有無、喫煙習慣などによって治癒のスピードは異なります。特に糖尿病や高血圧の方、また喫煙される方は治りが遅くなる傾向があるため、医師の判断で数日延期する場合もあります。
抜糸のタイミングは患者様ごとに慎重に見極められるものです。自己判断で早めたり、反対に来院を遅らせたりせず、必ず歯科医院の指示に従うようにしましょう。
一次手術・二次手術での違い
インプラント治療では、手術の段階によって抜糸のタイミングや注意点が異なります。一般的に「一次手術」と「二次手術」に分かれており、それぞれで歯ぐきの切開範囲や治癒のスピードが異なるのです。
一次手術は、インプラント体(人工の歯根)を顎の骨に埋め込む際に行う処置です。歯ぐきを大きく切開して埋入部を確保するため、創部が広く、抜糸の際も慎重な対応が必要です。抜糸の目安は7〜10日後で、腫れや違和感が残っている場合は医師の判断で数日延長することもあります。
一方、二次手術は、骨とインプラント体の結合を確認したうえで、歯ぐきの上にヒーリングアバットメントという金属パーツを装着する処置です。切開範囲が狭く、抜糸時の痛みも少ないことが特徴です。
どちらの手術後も、抜糸は治癒を確認する大切なステップです。手術の段階を問わず、自己判断せずに必ず医師の指示に従いましょう。
抜糸が遅れた場合のリスク
インプラント手術後の抜糸は、適切な時期に行うことが非常に重要です。もし抜糸が遅れてしまうと、糸の周囲に細菌が繁殖し、炎症や感染を引き起こすリスクが高まります。特に口腔内は常に湿度が高く、食べかすやプラークが付着しやすいため、長期間糸が残っている状態は不衛生になりやすいのです。
さらに、糸が歯ぐきに食い込んで刺激を与え続けることで、傷口が開いたり、治りが遅れたりすることもあります。場合によっては腫れや膿が出て、再度縫合や抗菌薬による治療が必要になることもあります。
「痛くないから大丈夫」と自己判断して来院を遅らせることは避けましょう。たとえ症状がなくても、2週間以上経っても糸が残っている場合は必ず歯科医院を受診してください。抜糸は数分で終わる処置ですが、放置による感染や炎症は長引くことがあります。早めの対応が、治療全体の成功につながります。
抜糸までの過ごし方:食事・清掃・生活習慣

抜糸までの期間は、傷口の治りを妨げないように過ごすことが大切です。インプラント手術後の歯ぐきはまだデリケートな状態にあり、少しの刺激でも出血や炎症を起こすことがあります。そのため、無理に食事をしたり、強く歯を磨いたりすることは避けましょう。
特に注意したいのは「温度」「刺激」「圧力」です。熱い食べ物やアルコール、激しい運動は血流を促進し、出血を再発させることがあります。また、硬い食材を噛むと縫合部に力がかかり、治癒を遅らせてしまうこともあります。
歯磨きは手術部位を避けて優しく行い、うがいは強く行わず軽くゆすぐ程度に留めます。清潔を保つことは大切ですが、過度な刺激は逆効果になるため注意が必要です。
喫煙も創傷治癒を遅らせる大きな要因です。最低でも抜糸までは禁煙を心がけ、身体の回復を助けるようにしましょう。
食事のポイント
抜糸までの期間は、傷口を刺激しないやわらかい食事を心がけることが大切です。手術直後から数日間は、硬いもの・熱いもの・辛いものを避け、冷たくて口当たりのやさしい食事を中心にすると安心です。
具体的には、豆腐・茶碗蒸し・ヨーグルト・白身魚の煮付け・おかゆなどが適しています。これらは栄養を補いながらも噛む力をあまり必要としないため、手術部位への負担を最小限に抑えることができます。反対に、唐揚げやせんべいなどの硬い食品、唐辛子やカレーなどの刺激物は、傷口を刺激して痛みや出血を引き起こすおそれがあります。
また、飲み物の温度にも注意が必要です。熱すぎるスープやお茶は血管を拡張させて出血を招くことがあるため、常温またはやや冷たい状態で摂取しましょう。
適切な食事管理は、抜糸までの治癒をスムーズにし、痛みや腫れを防ぐうえで欠かせないポイントです。
歯磨き・洗口剤の使い方
抜糸までの間は、口腔内を清潔に保つことが治癒を早めるうえで非常に重要です。ただし、手術部位に直接ブラシを当てると、縫合部分が刺激されて出血したり、糸が外れたりするおそれがあります。そのため、抜糸までは患部を避け、他の歯だけを軽くブラッシングするようにしましょう。
歯磨きの際は、毛先がやわらかい歯ブラシを使用し、強くこすらずやさしく動かします。手術部位に食べかすが付着して気になる場合は、軽くうがいをして流す程度にとどめます。
また、歯科医院でクロルヘキシジンなどの洗口剤が処方された場合は、指示された濃度と回数を守って使用します。アルコールを含む市販のマウスウォッシュは刺激が強く、患部にしみることがあるため避けた方が安心です。
清潔を保ちながらも、歯ぐきに負担をかけないケアを意識することで、炎症や感染を防ぎ、より早い治癒が期待できます。
喫煙・飲酒・運動・入浴
インプラント手術後から抜糸までの期間は、生活習慣にも注意が必要です。特に喫煙や飲酒、激しい運動、長時間の入浴は、いずれも血流に影響を与え、出血や腫れの原因となることがあります。
喫煙は血管を収縮させ、創部への酸素供給を妨げます。その結果、傷の治りが遅れたり、感染のリスクが高まったりするため、最低でも抜糸までは禁煙することが望ましいです。可能であれば、インプラント治療全体の成功率を高めるために、禁煙を継続するのが理想です。
また、飲酒や激しい運動、長風呂は血管を拡張させ、出血や腫れを引き起こす原因になります。どうしても入浴したい場合は、短時間のシャワーで済ませましょう。
この期間を安静に過ごすことで、出血や痛みを防ぎ、インプラント周囲の組織が安定していきます。体をいたわる生活が、良好な治癒につながるのです。
抜糸当日の流れと痛みの程度

インプラントの抜糸は、通常10分ほどで終わる簡単な処置です。多くの場合、麻酔を使用する必要はなく、患者様の負担も最小限に抑えられます。処置の流れとしては、まず創部の状態を確認し、炎症や腫れがないことを確かめたうえで、ピンセットやハサミのような専用器具を使って糸を一つずつ丁寧に取り除いていきます。
抜糸の際に感じる痛みは「チクッ」とした軽い刺激程度で、強い痛みを感じることはほとんどありません。処置後に少量の出血が見られることもありますが、ガーゼで軽く圧迫すれば数分で止まります。
抜糸後はすぐに日常生活に戻ることができ、食事もその日のうちに可能なケースが多く見られます。ただし、抜糸後数時間は創部がやや敏感なため、刺激の強い食べ物や熱い飲み物は避けましょう。
痛みが不安な場合でも、無理な我慢はせず、歯科医師に気軽に相談することで安心して処置を受けられます。
痛みや腫れが残る場合
抜糸後は通常、1〜2日ほどで違和感が落ち着いていきます。軽いチクチク感や引きつれたような感覚が残ることもありますが、多くは自然に治まるため心配はいりません。
しかし、抜糸から3日以上経っても痛みや腫れが続く場合は注意が必要です。特に、患部が赤く腫れている・ズキズキと痛む・膿のようなものが出ているといった症状がある場合は、細菌感染や縫合部の開きが起きている可能性があります。このようなときは自己判断で様子を見るのではなく、早めに歯科医院を受診しましょう。
再診時には、必要に応じて抗菌薬の処方や洗浄、場合によっては再縫合を行うこともあります。症状が軽いうちに対応すれば治りも早く、インプラントへの影響も最小限に抑えられます。
「痛みがあるのは普通」と放置せず、少しでも違和感が長引く場合は早めの相談が大切です。適切な処置によって、治癒を確実に進めることができます。
よくあるトラブルと対処法

抜糸の時期や経過が順調であっても、まれに想定外のトラブルが起こることがあります。多くは軽度のもので、早めに対応すれば大きな問題にはなりません。代表的なケースを知っておくことで、慌てずに対処できます。
まず、「糸が途中で取れた」「結び目が解けた」といった場合は、無理に引っ張ったり切ったりせず、そのままの状態で受診してください。無理に触ると傷口が開いたり、感染の原因になることがあります。
次に、「傷口が少し開いてしまった」場合は、うがいを控え、患部を清潔に保ちながら安静に過ごします。通常は自然に閉じますが、症状が強い場合は再縫合が必要です。
また、「出血が止まらない」場合は、清潔なガーゼを軽く噛んで10分ほど圧迫してください。それでも止まらない場合はすぐに歯科医院へ連絡を。早期対応によって、感染や炎症を防ぐことができます。
抜糸しないケース:吸収性糸が使われた場合
インプラント手術では、糸の種類によっては抜糸を行わない場合もあります。代表的なのが「吸収性縫合糸」を使用したケースです。この糸は体内で自然に分解・吸収されるため、物理的に取り除く必要がありません。
吸収性糸は、患者様の通院負担を軽減できるというメリットがあります。多くは2〜3週間ほどで体内に吸収され、糸が自然に消失していきます。ただし、体質や治癒経過によっては完全に溶けず、一部が残って違和感を生じることもあります。
もし糸の一部が残ってチクチクしたり、歯ぐきから飛び出して見える場合は、自己判断で引っ張らず、歯科医院で除去してもらいましょう。残った糸を放置すると、刺激や炎症の原因になることがあります。
吸収性糸を使った場合も、手術後の経過観察は欠かせません。歯科医師の指示どおりに来院し、治癒状態を確認してもらうことが大切です。
抜糸後の過ごし方:いつから普段どおりに?
抜糸が終わると、インプラント治療の一つの区切りを迎えます。処置後はほとんどの場合、当日から軽い食事や歯磨きが可能ですが、まだ歯ぐきの内部は完全に治りきっていないため、数日は注意が必要です。
抜糸直後の食事は、やわらかく刺激の少ないものを選びましょう。強く噛む動作や熱い飲み物は、傷口を刺激する原因になります。1〜2日経てばほとんどの方が普段どおりの食事に戻れますが、創部の違和感が残る場合は無理をせず、少しずつ慣らしていくことが大切です。
飲酒や喫煙、サウナなど血流を促進する行為は、抜糸後48時間ほど控えたほうが安心です。血行が良くなりすぎると、出血や腫れを再発させるおそれがあります。
適切なケアを続けることで、インプラント周囲の組織は安定し、最終的な被せ物の装着へとスムーズに進むことができます。抜糸後も油断せず、丁寧なセルフケアを心がけましょう。
のだ歯科クリニックの抜糸・術後フォロー方針

のだ歯科クリニックでは、インプラント手術後の抜糸を「治癒経過を見極める大切なステップ」と位置づけています。CTや拡大鏡を用いて創部の状態を正確に確認し、最も安全で適切なタイミングで抜糸を行います。
処置の際は、患者様の痛みや不安を最小限にすることを重視しています。抜糸前には必ず手順や所要時間、注意点を丁寧に説明し、痛みが苦手な方にも安心して受けていただけるよう配慮しています。女性医師も在籍しており、細やかな対応を希望される方にも好評です。
また、当院では担当衛生士制を採用し、抜糸後の清掃方法や生活上の注意点を継続的にサポートしています。術後の経過に不安がある場合や、他院で手術を受けた方の抜糸・経過確認にも対応可能です。
インプラント治療を「埋めたら終わり」にせず、抜糸からメンテナンスまでを一貫して支える。それが、のだ歯科クリニックの基本方針です。
関連するお悩みと解決策
抜糸後に「まだ少し痛みが残る」「歯ぐきがしみる」「インプラントのまわりが腫れてきた」といった症状が出ることがあります。多くは一時的なものですが、症状が長引く場合や強くなる場合は、早めの診査が必要です。
とくに、抜糸後の炎症を放置すると「インプラント周囲炎」へと進行するおそれがあります。これは、インプラントを支える骨や歯ぐきが細菌感染を起こし、最悪の場合インプラントが動揺・脱落してしまうこともある病気です。早期に歯科医院での洗浄やクリーニングを受けることで、症状の進行を防げます。
また、抜糸後の違和感が続く場合は、噛み合わせや清掃状態が関係しているケースもあります。必要に応じて咬合調整や再チェックを行うことで、快適な状態を取り戻せます。
のだ歯科クリニックでは、インプラント治療後のフォロー体制を重視し、痛み・腫れ・不安を感じたときにすぐ相談できる環境を整えています。
まとめ:抜糸は治癒の第一歩。違和感があれば早めに相談を

インプラント手術後の抜糸は、傷の治りを確認し、感染を防ぐための大切な工程です。多くの場合、手術から7〜10日後に行われ、処置自体は短時間で痛みもほとんどありません。抜糸を適切な時期に行うことで、歯ぐきの治癒が順調に進み、最終的なインプラントの安定にもつながります。
ただし、抜糸後に腫れや出血、痛みが長く続く場合は、感染や傷口のトラブルが起きている可能性があります。そのまま放置せず、早めに歯科医院で確認を受けることが大切です。
のだ歯科クリニックでは、抜糸からメンテナンスまでを一貫してサポートし、患者様が安心して治療を進められるよう丁寧にフォローしています。術後の不安や違和感がある方も、ぜひ一度ご相談ください。
関連記事
2026.01.14
部分入れ歯ができるまでの仮歯(仮入れ歯)とは|歯がない期間をどう過ごす?
2025.12.31
ホワイトニングがめちゃくちゃ痛い…寝れない原因と対処法|歯医者に行く目安も解説
2025.12.26
ホワイトニングは歯医者とサロンどっち?歯医者の方がいい理由・違い・値段・後悔しない選び方
2025.12.19